介護・福祉業界の人材確保を成功させるには?課題・具体策・事例を徹底解説
公開日:2025/09/18 更新日:2025/11/17
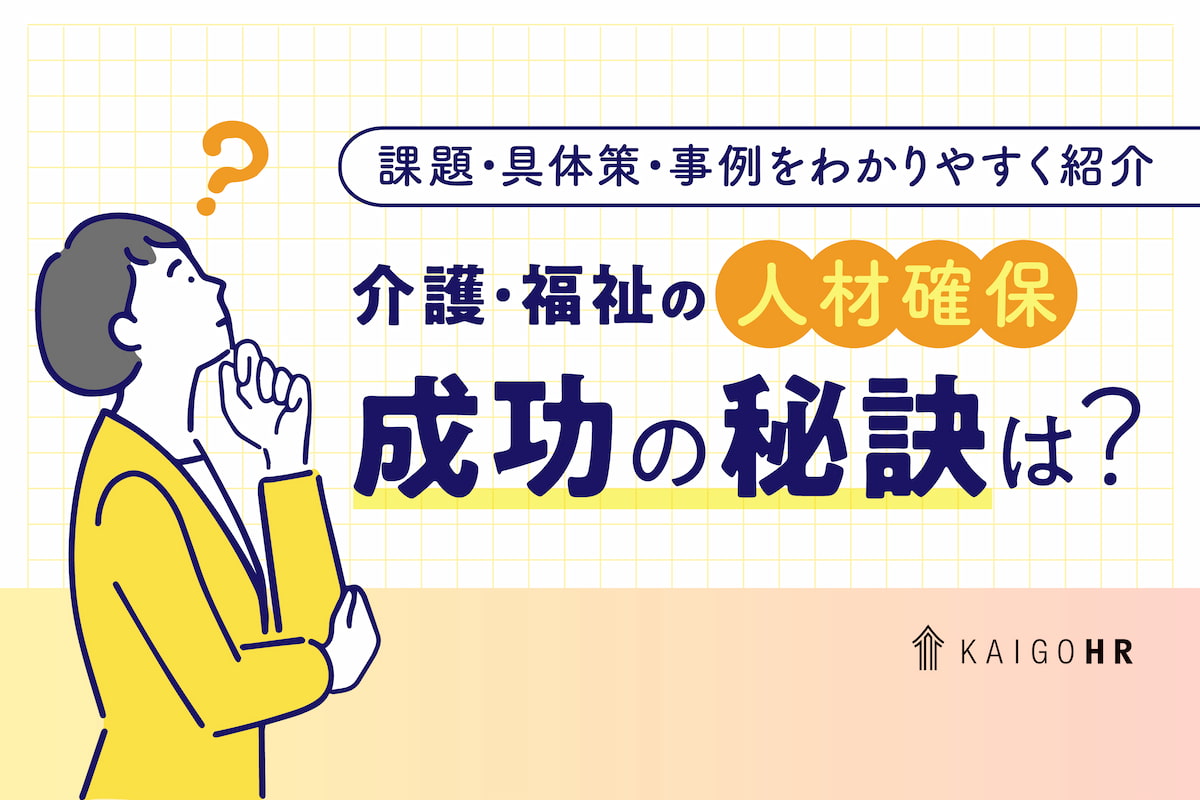
介護・福祉の現場では、人材不足が長年の課題となっています。
人材を確保し現場の負担を減らすためには、単に応募者数を増やすだけでなく、理念や職場環境の魅力をしっかり伝え、定着につなげる仕組みが重要です。
そこで今回は、介護・福祉分野の人材採用を専門とするコンサルタントが、なぜ人材確保が難しいのか、どうすれば採用を成功させられるのかを解説します。
国や自治体による支援制度の概要や現場での活用方法、そして実際の成功事例も交えて紹介するので、ぜひ介護・福祉現場の人事・採用担当者の方は参考にしてください。

【監修者】
野沢 悠介
株式会社Blanket取締役 / 人事コンサルタント / ワークショップデザイナー / 国家資格キャリアコンサルタント / Career Development Adviser
なぜ今、介護・福祉業界で人材確保が急務なのか

介護・福祉現場では、今後さらに深刻な人材不足が見込まれています。これは施設運営やサービス品質だけでなく、現場職員の離職リスクにも直結するため、経営・採用担当者にとって早急な解決を求められる課題です。
介護・福祉現場に必要な人材数と深刻な不足状況
厚生労働省の推計では、令和8(2026)年度には約240万人(※1)の介護・福祉人材が必要とされています。しかし、令和5(2023)年10月1日時点での介護・福祉職員数は約212.6万人にとどまり、前年(令和4年)より約3万人減少しています(※2)。令和元年以降の増減を見ても、年間で1〜3万人程度の微増にとどまり、大幅な改善は見られません。
一方で、要介護・福祉認定を受ける高齢者数は団塊の世代の後期高齢者入りにより右肩上がりで増加しています。このままでは、限られた職員がより多くの利用者を支える構図になり、介護・福祉職員一人ひとりの業務負担は確実に増えていくことが明らかです。
負担増は心身の疲弊を招くだけなく、一人あたりの業務が過重になることで介護・福祉職離れが加速し、離職率の上昇にも直結します。その結果、サービスの質の低下やそれによる利用者数の縮小といった、施設運営そのものにも影響を与える可能性も危惧されています。
こうした背景から、採用担当者は「人が減ってから慌てて募集する」のではなく、将来を見据えた計画的な採用と定着策の両立が求められています。
採用の姿勢が「来るもの拒まず」だと、職場に合わない人を迎える原因となり、双方にとって良い結果にはなりません。どんな人が合うのか、どんな人に来てほしいかという視点が非常に重要になります。
※1 介護・福祉人材確保に向けた取組について | 厚生労働省
※2 介護・福祉職員数の推移の更新(令和5年分)について| 厚生労働省
介護・福祉業界で人材確保が難しい3つの根本原因

介護・福祉業界の人材不足が続く背景には、単純に「応募者が少ない」だけでなく、応募者が集まらない根本的な原因があります。
ここでは、人材確保に特に影響の大きい3つの要因について解説します。
業務の負担感と低賃金のギャップ
令和6年の常勤介護・福祉職員の平均基本給は25万5,400円(厚生労働省調査)です(※1)。一方で、産業計(全産業平均)の所定内給与額は33万400円となっています(※2)。
| 常勤介護・福祉職員の平均基本給 | 25万5,400円 |
| 全産業平均 | 33万400円 |
統計上の定義が異なるため単純比較はできませんが、介護・福祉職は身体的・精神的な負担が大きいにもかかわらず、平均給与は他業界より低い水準にとどまっているといえます。
この「ギャップ」が、人材確保の大きなハードルとなっていることは明らかです。
介護職員の処遇改善は国全体で一定進み、以前より賃金は上がっています。一方で、介護報酬という制度上の上限があるため、企業努力による柔軟な賃上げが難しく、他業種との賃金格差は依然として残っています。
むしろ最近の賃上げの流れで、その差が広がる面もあり、結果として、「業務の難しさや負担に比べて賃金が見合わない」と感じる人が少なくないのが現状です。
※1 賃金構造基本統計調査 / 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種|政府統計の総合窓口
※2 「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果を公表します|厚生労働省
働きづらさ(人間関係・シフト・ライフイベント)
介護・福祉現場では、人間関係の悩みが離職理由としてよく挙げられます。
人間関係に起因する離職は、介護・福祉業界特有というわけではなく、その他の業種でも多く見受けられます。しかし一般的な企業よりも、より密なコミュニケーションを必要とする対人援助職の特性や、年齢・職種・キャリアなどが入り混じる介護・福祉業界の職場構造にストレスを感じる人も少なくありません。
さらに土日勤務や夜勤などが発生することから、子育てや家族の介護・福祉との両立が難しいケースも目立ちます。柔軟な働き方が取りにくい環境では、特に女性や中高年層が長く働き続けるハードルが上がります。
現在の介護・福祉現場では、さまざまなバックグラウンドを持つ人が働く事業所が多くあります。そのため、年齢や経験の違いから上下関係のギャップを感じる人が出ることも少なくありません。
キャリアパスや成長機会の不透明さ
他業種に比べて給与水準が低く、かつキャリアアップの仕組みが整っていない職場が多いことも、介護・福祉業界の人手不足を増長する原因です。
「資格を取っても昇給しない」「将来のキャリアが見えない」と感じれば、長期的に同じ施設や会社で働く動機を見失ってしまい、人材流出を招いてしまいます。
そのため採用側は求人時点でキャリアパスや昇給のルートを設計した上で明確に示し、長期的に働くイメージを持ってもらう工夫が必要です。
今すぐ実践!介護・福祉人材確保に効果的な4つの施策

人材確保が難航する中で、「誰でもいいから」と採用活動を無計画に行ってしまうと、仮に採用につながったとしても、入職後のミスマッチが生じ、トラブルや早期離職につながるリスクも高まります。
そうならないように、日ごろから「求める人材が応募しやすく、長く働きやすい環境と仕組み」を整えておくことが重要になります。
ここでは比較的取り組みやすく、成果につながりやすい4つの人材確保の方法を紹介します。
(1)求人サイトを活用して応募数を増やす
人材確保といえば、求人サイトの活用を検討する施設も多いことでしょう。大手の求人サイトは幅広い求職者層にリーチできるため、一定の応募数を確保しやすい手段です。
ただし閲覧数が多い反面、介護・福祉未経験者や他業種からの応募も多数あります。そのため求める人物像や仕事内容を明確に打ち出さないと、ミスマッチが増えて施設側の負担ばかりが増えてしまうことも考えられます。
こうした問題を防ぐためには、介護・福祉職専門の求人サイトや、ターゲット層が利用するプラットフォームを選定し、求人原稿の内容や写真、タイトルなどを戦略的に工夫しましょう。
(2)ハローワークで地域密着の人材を採用する
ハローワークは無料で求人を掲載できる点が大きな魅力です。公的機関によるサービスという点にも、安心感があります。
ただし、求職者のスキルや就業意欲には幅があり、中には「とりあえず就職活動をしている」「失業保険が目的」というケースも少なくありません。
ハローワークは「母集団形成の入口」として有効です。ただし掲載するだけでは成果が出にくいため、求人票の工夫や他施策との組み合わせがカギとなります。
(3)リファラル採用で信頼できる人材を確保する
現職員からの紹介を通じて採用するリファラル採用は、入職後の定着率が高い傾向にあります。既存社員を通して、職場の雰囲気や業務内容を事前に聞けるため、入職後のギャップが小さいことに加え、定着までに現職員のフォローがあるためです。
リファラル採用を促すためには、現場の満足度向上が不可欠です。さらに、紹介インセンティブの仕組みを設けるといった施策を取り入れることで、リファラル採用数の増加につながります。
(4)自社サイトで職場の魅力を発信し採用につなげる
自社採用ページやコーポレートサイトを活用し、働く人の声や1日の流れ、施設の雰囲気などを発信するのも、人材確保において有効な方法です。SNSと連動させれば、より拡散力が高まり、求人媒体を見ない層へのアプローチも可能になります。
ただし更新が滞ると、現状を詳しく伝えることができず、人材確保につながらなくなります。社内で更新担当を決めるか、制作を外注する体制を整えるなど、無理なく発信を継続できる環境を整えましょう。
また、写真や動画を使ったビジュアル訴求ができるのも、自社サイトならではの強みです。
上記施策を行えば、直ちに人材確保につながるという訳ではありません。各施策に共通して重要なのは「誰に向けて発信するか」というターゲットの設定と、「自分たちの強み・特徴・大切にしていることは何か」という訴求内容の整理です。
これらをしっかりと行った上で、各ツールの強み・特徴を活かしたアクションを行うことが重要です。
国や自治体の介護・福祉人材確保に向けた主な取り組みと支援制度
採用担当者にとって、国や自治体が実施する制度や補助は、心強い味方になります。
ここでは、求人の魅力を高め応募者の不安を減らすために活用できる制度を、いくつか紹介します。
研修補助制度(初任者研修・実務者研修など)
未経験者や異業種からの採用を後押しするため、国と自治体は「介護・福祉に関する入門的研修」や資格取得支援を行っています。
入門的研修はおおむね21時間で、介護・福祉の基礎を学べる内容です。自治体によっては、研修→職場体験→就職まで、トータルでサポートするケースもあります。
さらに、雇用保険の「教育訓練給付制度」を使えば、初任者研修は最大50%、実務者研修など長期課程は最大80%まで、受講料の補助を受けられる場合もあります。
未経験者を採用する際は、入職前後のサポートの有無が重要です。活用できる制度の詳細をしっかり把握し、入職後の資格取得のサポート体制があることを明示することは、未経験者にとっては入職前の安心材料になります。
【参考】
介護・福祉人材採用に向けた事例集|厚生労働省
入門的研修の概要|厚生労働省
処遇改善加算・特定処遇改善加算の活用
令和6年度の介護・福祉報酬改定で、従来の複数加算が「介護・福祉職員等処遇改善加算」に一本化されました。
加算を受けるには、経験や技能のある職員への重点配分、キャリアパスの整備、職場環境改善の取り組みが条件です。
【参考】
介護・福祉職員の処遇改善 | 厚生労働省
介護・福祉サービス事業者認証評価制度
介護・福祉サービス事業者認証評価制度は、職員育成や働きやすい環境整備に取り組む事業者を、都道府県が認証する制度です。
認証を受けると求人時の信頼度が上がり、応募者から「安心して働けそう」と評価されやすくなります。
制度や基準は自治体によって異なるため、要件を確認して申請を検討しましょう。
認証は地域によって要件が異なります。制度活用を検討する際は、ぜひBlanketにご相談ください。認証を受けることが貴法人にメリットがあるか、認証後にどのように人材確保施策につなげるかも含めてご案内いたします。
自治体独自の支援制度や助成金
職場環境改善や生産性向上を目的とした独自の補助金・低利融資制度を設けている自治体もあります。
たとえば、東京都では「介護・福祉人材確保・職場環境改善等事業」を設け、設備導入や研修に補助金を支給する体制を整えています。大阪府では「生産性向上支援センター」を制定し、機器の試用や業務改善をサポートしています。
こうした支援は自治体によって内容が異なるため、自社のエリアの窓口に詳細を確認してみてください。
【参考】
令和7年度介護・福祉人材確保・職場環境改善等事業について|東京都介護・福祉サービス情報
介護・福祉人材確保・職場環境改善等事業について|大阪府ホームページ
介護・福祉現場で実際に効果があった人材確保のポイント

採用手法は数多くあります。しかし闇雲に採用手法を取り入れても、思うような効果は出にくいものです。
ここでは、介護・福祉現場の人材確保をサポートしているBlanketが行ってきた施策の中で、実際に成果があった取り組みを紹介します。
採用ターゲットの範囲を広げる
未経験者や異業種からの人材を積極的に取り入れることで、応募母数を増やせます。ただし「来るもの拒まず」ではミスマッチが増え、早期離職の原因になります。
そのため、採用ターゲットの範囲を広げる際には、以下のポイントを押さえることが大切です。
・採用要件を明確化し、誰に来てほしいかを事前に設定する
・未経験者を採用する場合は、受け入れフロー(役割説明・業務の伝え方)を整備し、入職後のフォロー体制を作る
・求人要件に「資格取得支援あり」や「研修体制あり」と記載し、安心感を与える
現場の求める人材を事前に把握する
現場が本当に必要としている人物像を理解して採用を進めることで、現職員の負担を減らすことができます。さらに、応募者も職場環境に馴染みやすくなることで離職率の低下にもつながります。
現場が求める人物像を把握するためには、現職員の声に耳を傾けるのが最適です。現場ではどのような課題を抱えているか、その課題を解決するためにはどういった人物像が必要なのかを、ヒアリングしてみましょう。
全員が満足する制度を実現するのは非常に困難です。そのためまずは残ってほしい人のために、何を整えるかを見極めることが大切です。
Blanket では、採用から定着まで一貫して支援しています。施設ごとの課題や強みに合わせた具体的な改善施策を提案し、数々の施設の人材確保に向けたサポートを行っています。
人材確保の取り組みは、その事業所の課題を踏まえて進めることが欠かせません。もし「人材育成が思うように進まない」「定着につながる仕組みをつくりたい」といったお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
介護・福祉現場の人材確保の成功事例
ここでは、自社の理念や特徴を生かした採用戦略で、必要な人材を確保した2つの事例をご紹介します。
どちらも自社らしさを全面に打ち出し、求職者の共感を得ることで採用の壁を乗り越えた取り組みです。
(1)社会福祉法人ケアネット

東京都中野区を拠点に地域密着の介護・福祉サービスを提供する社会福祉法人ケアネットは、新設した特別養護老人ホームのオープニングスタッフの採用計画を実施。
しかし、同地域は介護・福祉職の有効求人倍率が8倍超と「採用激戦区」に位置しており、人材確保が非常に困難な状況でした。
そこでBlanketとともに、会社の理念と、目指すのは「日本一居心地のよい住まい」という新施設への想いをコンセプトに据えた採用戦略を設計。特設採用サイトを制作し、ケアネット「らしさ」を全面に打ち出す採用計画を展開するとともに、定期的なミーティングを通じて状況に応じた支援を継続しました。
結果として、開設に必要なスタッフを無事確保することに成功。理念に基づいた情報発信によって、競争の激しい地域でも求職者の関心と応募を集めることができました。
(2)株式会社ゆず

広島県尾道市を拠点に介護・福祉・医療・保育サービスを展開する株式会社ゆずは、東広島市に看多機ホームとグループホームを開設しました。
これまで進出経験のなかった地域での開設のため、まずは「ゆずらしさ」をアピールするための採用コンセプト「いつまでも、どこまでも、FREE STYLE」を打ち出すことに。
この採用理念に共感できる人材をターゲットとし、特設採用ページの制作、さらに会社説明会ではゆずの想いや目指す姿を丁寧に発信しました。面接では一人ひとりとじっくり対話し、相互理解を深めることにも注力していました。
その結果、採用目標だった常勤介護・福祉職23名を無事確保することに成功。新しい地域でも理念に沿ったメンバーを迎え入れ、開設後は職員が一丸となってより良いチームづくりに励んでいます。
介護・福祉現場で人材を定着させる方法
介護・福祉現場で採用した人材を長く定着させるためには、まず自社の理念や大切にしている価値観を明確にし、それを日常の業務や評価制度に反映させることが重要です。理念が共有されていれば、職員は自分の仕事の意味や役割を実感しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。
とはいえ、すべての人に合う制度を整えるのは現実的ではありません。そこでまずは理念を基に自社が求める人物像を明確にし、その層に響く仕組みを優先的に整えることが効果的です。
加えて入職時だけでなく、その後も定期的に面談を継続し職員の現状の課題や不満を把握する姿勢を示すことも大切です。職員に安心感を与えモチベーション維持につながります。
また、介護・福祉ロボットやICT(介護・福祉記録のデジタル化、情報共有システムなど)の導入は、業務負担を減らし離職防止につながります。こうした効率化で生まれた時間を研修や休憩に充てれば、職員の満足度はさらに向上します。
多くの人は、職場に違和感を持った時点で離職の選択肢が頭に浮かんできます。大切なのは「働いて欲しい人に長く残ってもらえる」環境を整えることです。
まとめ
介護・福祉業界では人材確保が思うように進まず、既存職員の負担増や離職率の上昇が深刻化しています。
こうした状況を打開するには、人手不足の根本的な原因を知り、自社の体制に合った施策を取り入れることが大切です。また、国や自治体の制度活用に加え、成功事例を参考にすることも有効な手段となります。
採用は一度きりのイベントではなく、継続的な取り組みです。人が集まりにくい理由を明らかにしながら自社の改善点や伸ばすべきポイントも見極めて、適切な形で計画を継続していきましょう。
採用の難しさはどの事業所も感じていますが、原因と向き合い、自社に合う方法を続ければ必ず道は開けます。焦らず、一歩ずつ改善を積み重ねていきましょう。







