介護施設の求人になぜ応募がこない?改善策と応募を増やすコツを紹介
公開日:2025/10/31 更新日:2025/11/13

「求人を出しても応募がこない」「せっかく面接しても辞退される」「人材が定着しない」――。介護施設の採用現場では、そんな悩みを抱える声が後を絶ちません。
労働人口減少のあおりを受け、人材不足が続く介護・福祉業界。人材の確保・定着に向けて、待遇や環境の改善が進んでいるにもかかわらず、応募数はなかなか伸びないのが現状です。
では、なぜ介護・福祉職の求人には応募が集まりにくいのでしょうか?その背景には、未経験者・経験者それぞれの心理的なハードルや、求人内容の伝わり方に課題があることが見えてきます。
今回は、介護施設への応募がこない主な理由から、応募を増やすための具体的な改善策、さらに採用後の定着を見据えた育成ポイントまでを詳しく解説します。介護・福祉業界の採用コンサルタントによる分析・アドバイスも記載しておりますので、参考にしてみてください。
介護施設だけでなく、福祉業界でも役立つ視点やコツをまとめています。

【監修者】
太田 高貴
株式会社Blanket採用コンサルタント / 社会福祉士 / 一般社団法人総合経営管理協会 認定採用コンサルタント
介護施設の求人に応募がこないのはなぜ?よくある理由は?
介護業界は慢性的な人材不足に直面しています。求人数は多いものの、それに対して応募が少なく、「求人を出してもなかなか人が集まらない」という声は後を絶ちません。
実際には、給与や処遇改善の取り組みが進み、離職率は徐々に下がっています。公益財団法人介護労働安定センターの最新調査(※)によると、訪問介護職員と介護職員を合わせた2種の離職率は12.4% と、2年連続で低下しました。
その一方で、採用率も14.3%と3年ぶりに低下しました。つまり、新しい人材の確保が進んでいないため「離職する人は減っているのに、応募者は増えない」という状況が続いています。
待遇や環境が改善傾向にあるにもかかわらず、応募者が増えない原因はどこにあるのでしょうか。考えられる理由を整理しましょう。
※令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について|公益財団法人介護労働安定センター
未経験者が応募してこない理由

未経験者が応募してこない理由には、主に以下の3つが考えられます。
【仕事内容や必要スキルのイメージが湧かない】
介護・福祉職に関心を持っていても「自分にできるだろうか」という不安から、応募をためらう未経験者は少なくありません。
特に「資格がなければ働けない」という誤解が根強くあり、応募のハードルを高く感じてしまうケースが多くあります。実際には、介護・福祉職の求人には「未経験歓迎」「資格取得支援あり」といった条件が多く、まずは現場で経験を積みながらスキルアップしていく道が一般的です。
しかし、求人票だけでは仕事内容や求められるスキルが分かりにくく、結果的に「できるかどうかイメージできない」という壁が応募を阻んでいます。
【「介護=大変」というネガティブな印象が強い】
介護・福祉の仕事は「体力的に厳しい」「精神的にきつい」といったイメージが広く浸透しており、未経験者ほど応募を避ける傾向があります。
確かに、介護・福祉職は体を使う場面はあるものの、それは仕事の一部。記録を取ったり研修を受けたり事務作業をしたりといった業務もありますが、未経験者にはやはり肉体労働のイメージが強いといえます。
また、「労働環境が過酷なのでは」という不安もあるでしょう。しかし実際には、介護・福祉業界は行政による実地指導や監査が定期的に行われることもあり、残業代の支給や勤務環境の透明化が進んでいます。
そういったプラスのイメージが伝わらず、「選択肢の一つとして考えたが、やはり大変かもしれない」と考え直してしまう人も少なくありません。
介護・福祉業界は「ブラック」というイメージを持たれがちですが、サービス提供の質や運営体制に問題があれば改善指導が入り、重大な事案は公表されることもあります。こうした仕組みにより、極端に不適切な運営が長期間放置されることはまれです。
一方で、人手不足や業務量の多さといった課題は残っていますが、処遇改善加算や働き方改革の進展により、職員の待遇や職場環境の改善が進んでいます。業界全体として、より働きやすい環境づくりに向けた取り組みが広がっています。
【研修やサポート体制の不安から応募に踏み切れない】
未経験者が最も気にするのは「入職後にどんな研修やサポートがあるか」という点。求人票に研修制度の記載があっても、実際に何を学べるのか、きちんと業務で必要なスキルが身につくのかが分からなければ、「自分は働いていけるのだろうか」という不安は解消されません。「書いてはあるけれど、本当にサポートしてもらえるのだろうか」と疑念を抱かれ、応募を思いとどまってしまうのです。
応募につなげるには、たとえば「入職直後は先輩職員がマンツーマンで指導」「資格取得にかかる費用を施設が全額負担」といった具体的な内容を示しましょう。応募への安心感を与えられます。
経験者が応募を避ける理由

経験者の場合は、未経験者とはまた異なった視点や理由が考えられます。
【給与や待遇がスキルに見合っていない】
経験者の転職理由の一つが「給料」や「待遇」のアップです。介護・福祉の現場で経験を積んだ人ほど、自分のスキルや資格に見合った待遇を求めます。
雇用者側も経験者には即戦力として活躍すること、ゆくゆくは管理職として活躍することを求める傾向がありますが、求人によっては「求められる責任や夜勤シフトの負担に比べて、給与が見合わない」と感じられるケースが少なくありません。
一方で、働き方の面から介護・福祉業界から離れようと考える人もいます。介護・福祉職では夜勤や三交代勤務がある場合もありますが、これらは生活リズムが崩れやすく、長期的に続けることへの抵抗感を持つ人もいます。
給与や待遇が大きなネックとなり、応募を避けられてしまうのです。
【キャリアアップや成長の道筋が見えない】
介護・福祉職経験者にとって「今後どう成長していけるのか」は重要な判断基準です。入職後にどんなスキルを習得できるのか、管理職層へとキャリアアップできるのかが分からないと、応募にはつながりません。
特に、すでに介護業界で働いている人は「スキルを上げて収入を増やしたい」「成長できる環境に身を置きたい」と考えて転職先を探す人も一定数います。
その際に求人票でキャリアパスが提示されていなければ、「ここでは自分の将来が描けない」と判断され、応募を避けられてしまうのです。
【人間関係や職場環境への懸念がある】
転職を考える人は、これまでの経験から「人間関係」や「職場環境」を重視するケースもあります。
「前の職場では人間関係が大変だったから、次は安心できる環境で働きたい」など、給与や待遇ではなく、人間関係やチームワークを重視している人も少なくないでしょう。
しかし、求人票では内部の雰囲気や職員同士の関係性までは伝わりにくく、応募をためらう要因になってしまいます。経験者ほど「見えない部分」に敏感であり、それが応募の大きな壁になっているのです。
介護施設の求人応募を増やすために取り組むべき4STEP

介護・福祉施設が応募数を増やすためには、求職者の心理に寄り添うことが大切。そして自施設に合う人材を明確にし、魅力を適切に発信していく取り組みが欠かせません。ここでは、応募を増やすために施設側が取り組むべき主なポイントを解説します。
大切なのは、ターゲットを設定して、そのターゲットに合わせたPR手法・内容を考えて実践していくこと。STEP1〜4を実践できているかチェックしてみましょう。
STEP1:どんな人に来て欲しいのかターゲットを明確にする
採用活動では、施設の理念や方針に基づいたターゲットを設定し、「どんな人に来て欲しいのか」をできる限り明確にイメージすることが大切です。
たとえば「利用者さんに寄り添うケアを大切にできる人」「利用者さんと信頼関係を築ける人」「チームワークを重視して仕事ができる人」「現在のチームを引っ張っていってくれる管理層」など、施設ごとの価値観や求める人材に沿ったターゲットを設定しましょう。
採用は「入職して終わり」ではなく、長く定着して活躍してもらうことが目的です。そのためにも、理念への共感があるかどうかは非常に重要な要素です。
なお、ターゲットを設定する際は、実際に現場で活躍している職員をモデルに考えると、よりリアルで効果的な人物像を描くことができます。
STEP2:職場の雰囲気や働く人の声を可視化する

応募者が最も気にするのは「自分に合う職場かどうか」。職場の雰囲気が見えないままでは、応募に踏み切れません。不安を解消するには、職員インタビューや日常風景の写真・動画、SNSでの発信など、リアルな情報を可視化することが有効です。
自分と似た経歴の人が活躍しているのかどうか、家庭との両立が叶うのかどうかを実際の職員インタビューから分かるようにしましょう。“職場の風通しの良さ”や“働きやすさ”が伝わるはずです。
また、正式に応募する前に“カジュアルな面談”の機会を設けたり、入社する前に“お試し入社”や“体験勤務”の機会を設けたりするのも効果的です。週1〜2回の勤務から始め、互いの相性を確認してから本採用につなげることで、ミスマッチや早期離職を防ぐことができます。
こうした制度は求職者にとっても安心材料となり、応募へのハードルも下げることができます。
職場の雰囲気を伝えるためには「お試し期間」の導入がとても有効です。
一例として、いきなり正社員として雇うのではなく、週に数回の勤務からスタートし、互いに「合う」と感じたタイミングで正社員登用するケースもあります。こうした“試す採用”はミスマッチを防ぐうえでも効果的です。
STEP3:柔軟な勤務体系や子育てとの両立支援を打ち出す
応募者のライフスタイルに寄り添った働き方の提案も、応募を増やすポイントです。特に子育て世代や副業希望者など、柔軟な勤務を求める層に対しては「時短勤務」「日勤のみ」「週3日勤務可」などの制度を明確に打ち出すことが効果的です。
また、「10時出勤・16時退勤」「土日休み可」など、具体的な勤務スケジュールを記載することで、求職者が自分の生活と照らし合わせてイメージしやすくなります。
経験者の中には「より自分に合った働き方を選びたい」と考える人も多いため、柔軟性を示すことで応募対象を広げることができます。
職員インタビューで、職員の勤務体系の一例を掲載するのも効果的です。
STEP4:求人媒体に合わせた情報発信と改善を続ける
求人媒体ごとに掲載内容を最適化することも、応募率を上げる重要なポイントです。
たとえば、総合求人サイトでは未経験者の目に留まりやすいように、研修制度や教育サポートを詳しく掲載すると効果的です。また、介護業界の働き方やキャリア形成をわかりやすく紹介する資料を添えることで、未経験からの応募につながりやすくなります。
一方、介護専門の求人サイトでは、施設の理念や提供しているサービスの特徴をより深く打ち出しましょう。「どんな介護を目指しているのか」「利用者に対してどんな姿勢を大切にしているのか」を明確に伝えることで、志向の合う経験者の応募を引き寄せることができます。
求人は一度出して終わりではなく、反応を見ながら改善・更新を繰り返すことが鍵となります。
総合求人サイトを使用する人と、介護専門の求人サイトを使用する人では注目するポイントが変わります。介護専門サイトでは、“自施設と他施設との違い”をより明確に記載するのが望ましいです。
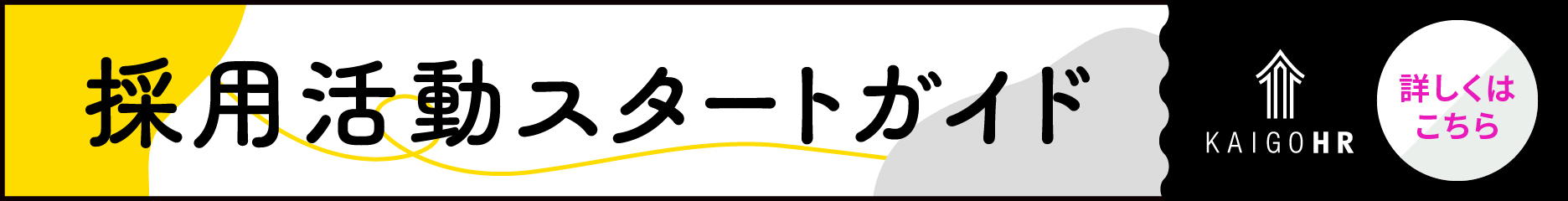
介護・福祉業界の採用コンサルタントが解説!応募を増やすためのポイント

介護・福祉業界の採用では、「どうすれば応募してもらえるか」だけでなく、「どうすれば共感してもらえるか」が重要です。ここでは、現場を知る採用コンサルタントの視点から、未経験者・経験者それぞれに響く採用アプローチを紹介します。
未経験者が「応募してみよう」と思える工夫
未経験者が最も抱えているのは、「自分にもできるのだろうか」という不安です。そのため、育成制度や研修体制が整っていることをしっかり伝えることは基本。しかし、それだけでは十分ではありません。ほとんどの施設では、研修を設けているため、差がつきにくいからです。
効果的なのは、「自分と似た経歴の人が活躍している」ことを見せること。たとえば、「元販売職の職員が今は介護リーダーに」といった事例を、インタビュー記事や動画で紹介するとリアリティが伝わります。求めるターゲットに近い現役職員に登場してもらうことで、応募者は「自分もできるかも」と具体的に想像できるようになります。
また、いきなり応募を促すのではなく、「まずは話を聞いてみませんか?」というカジュアル面談を挟むのも効果的です。緊張を和らげ、自然な形で施設の雰囲気を感じてもらうことができます。
採用担当者も成果を求められる立場なので、「誰でもいいから入ってほしい」と思ってしまうことがあります。気持ちは分かりますが、結局ミスマッチが起きて早期退職につながる可能性も……。
“数”ももちろん大切ですが、それに加え、“共感してくれる人”を採用することも重要。時間をかけて信頼を築き、「この施設で働きたい」と惚れてもらえる関係を目指すことが、長期的には一番の近道です。
経験者が「ここで働きたい」と思える工夫
経験者の応募を増やすには、「当法人でキャリアの希望をどう実現できるか」を明確に伝えることが重要です。介護経験者が転職先選びで重視するのは、「キャリアアップできるか」「自分の理想の介護を実践できるか」「ライフステージが変わっても働き続けられるか」などです。
つまり、「うちなら本当の個別ケアができます」「専門資格の取得支援制度があります」「ライフスタイルに合わせた勤務ができます」など、自分たちの強み・特徴を正しく知ってもらうことで、共感が生まれ、応募・採用につながっていきます。
また、柔軟な働き方を望む人に対しては、実際の勤務スケジュールを例示して具体的に伝えましょう。「週4勤務で夜勤なしのスタッフがこう働いています」など、リアルなケースを紹介すると信頼度が高まります。
採用は「選ぶ」だけでなく「選ばれる」ものでもあります。求職者が質問しやすい空気を作り、どんな質問にも正直に答えられる準備をしておくことも大切です。
誠実な姿勢が伝わる施設こそ、求職者から「ここで働きたい」と思われるのです。
Blanketでは、介護・福祉業界の法人や事業所を対象に、採用や人材定着に関するコンサルティングサービスを提供しています。
「応募が集まらない」「せっかく採用しても定着しない」など、現場で抱える課題に合わせて、採用戦略の設計から人材育成体系の構築まで、最適なプランをご提案しています。まずは現状に合ったサポートプランを確認してみませんか?
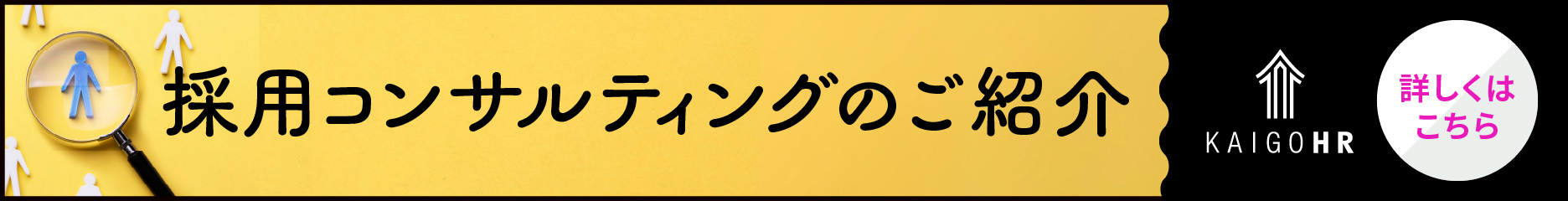
採用後の体制も重要!育成と定着のポイント

応募を集めることはゴールではなくスタート。入職しても早期離職してしまっては、人手不足は解消されません。“入職後の育成”と“定着の仕組み”を整えることが、真に意味のある採用活動につながります。
形だけの制度ではなく、「実際に機能しているのか」を見せることが大切です。マニュアルやキャリア設計など、具体的な仕組みを示すことで、応募者は“働く自分の姿”をより鮮明にイメージできます。
明確なキャリアパスを示す
採用者側が長期で働いてもらいたいと思っているのと同様に、応募者側も「ここで働き続けるとどんな成長ができるのか」「長期で働いていけるかどうか」が気になっているはず。そこで、明確なキャリアパスの提示です。
たとえば「入職1年目で基礎業務を習得し、3〜5年目にはリーダー職、5〜10年目には管理者候補へ」といった具体的なステップを見せたり、実例があれば先輩職員のキャリアパス例を提示したりすることで、職員が将来像を描きやすくなります。
キャリアパスが見える化されていれば「数年後の姿」「働く自分の姿」をイメージしやすく、モチベーションの維持にもつながります。離職率の低下にも効果的です。
体系的な教育・研修制度を整える
新人教育で「OJTがあります」と説明する施設は多いですが、応募者が知りたいのは“どう機能しているのか”という点です。OJTだけでなく、マニュアルや研修プログラムを体系的に組み合わせることで、現場任せにならない教育体制を構築しましょう。
たとえば、業務マニュアルを整備して第三者が内容をチェックする体制を設けたり、「入職3か月後には○○業務ができるようになる」といった明確な目標設定を提示したりすることで、安心して成長できる環境が伝わります。
また、モデルキャリアパスを提示すれば、「○カ月でここまでできるようになることが求められているんだ」と応募者が実感できるという面も。施設側が求めることと職員の現在のスキル位置が分かると、業務で起こり得るミスコミュニケーションを防ぐこともできるでしょう。
現段階で教育体制が整っていないのであれば、採用だけでなく、“受け入れ”や“育成”の仕組みづくりから強化していく必要があります。新しく入った人を迎える体制が整っている施設ほど、長く安心して働いてもらえる土壌ができています。
職員が孤立しない仕組みをつくる
どんなに教育制度が整っていても、職員が職場で孤立してしまう状況では長くは続きません。特に介護・福祉現場では、1人で判断する場面も多く、孤独感を覚えやすいもの。「誰にも助けを求められない」と精神的にいっぱいいっぱいになってしまわないよう、メンタル面のサポートが欠かせません。
そのためには、メンター制度やプリセプター制度など、先輩職員が新入職員をサポートする仕組みをつくることが重要です。定期的な面談や意見交換の場を設け、「困ったときに相談できる人がいる」という安心感を持てる環境を整えましょう。
メンタルサポート体制は非常に重要であるものの、そこまで手が回らないという事業所も少なくありません。そういった体制が体系的に整っていない場合でも嘘をつかず、今は“これから作っていく段階”であることを正直に伝え、その上で施設の理念や方針に共感してくれる人を採用することが大切です。
まとめ
介護・福祉施設の採用課題は、「応募が来ない」「採用しても定着しない」という2つの壁があります。しかしその多くは、求職者とのミスマッチや情報不足による“イメージのすれ違い”から生まれています。
応募を増やすためには、まず「どんな人に来てほしいのか」を明確にし、職場の雰囲気・育成体制・キャリアステップを見える化することが重要です。さらに、採用後も育成やフォローの仕組みを整え、「ここで長く働きたい」と思ってもらえる環境づくりまで一貫して取り組むことが、真の採用成功につながります。
法人・事業所の理念に共感し、長く活躍できる人材と出会うために、今できるポイントからひとつずつ取り組んでいきましょう。







