介護・福祉業界の中途採用を成功させる方法と具体的な手法を解説!
公開日:2025/08/19 更新日:2025/11/17
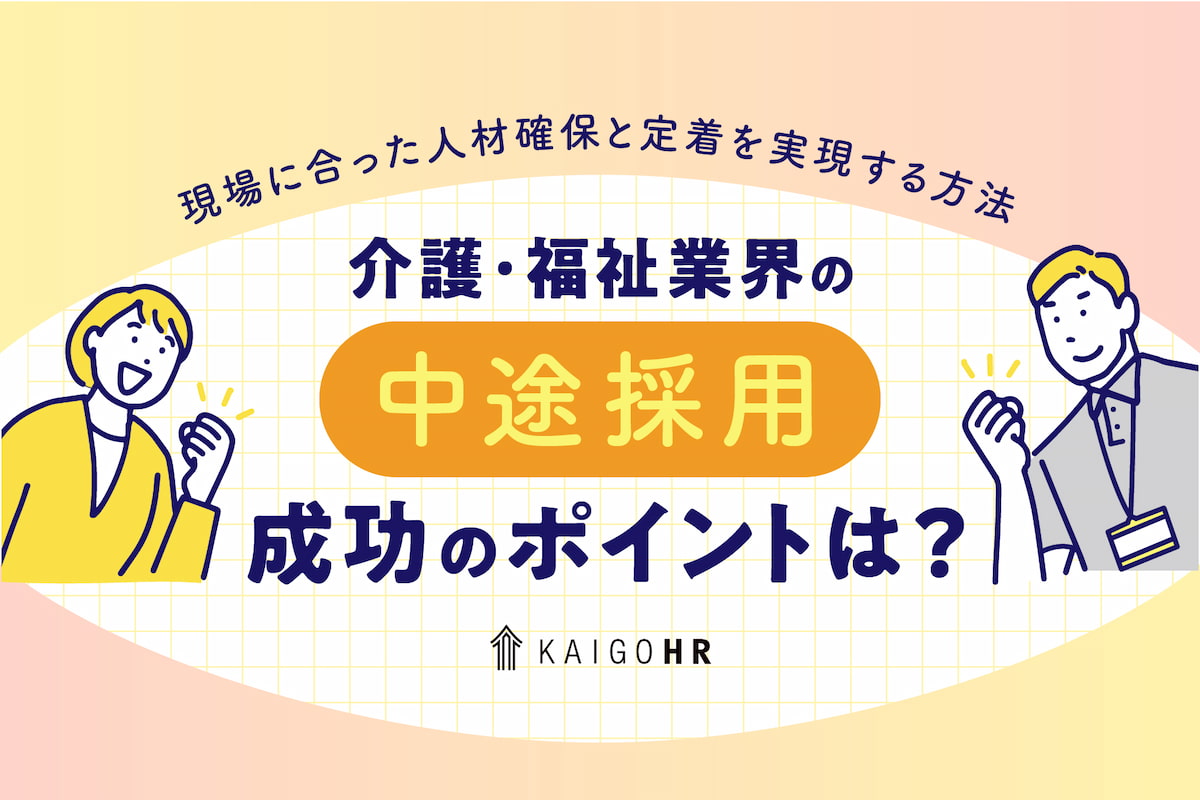
介護・福祉業界では慢性的な人手不足が続き、採用担当者にとっては常に「人材確保」が最優先の課題となっています。「早く人を入れてほしい」という現場の声に、プレッシャーを感じている採用担当の方も多いのではないでしょうか。
そんな現場のニーズに応え得る人材として期待されているのが「中途採用」です。中途採用のスタッフは社会人としての経験や、介護の現場で必要なスキルをすでに備えていることが多く、柔軟な活躍が期待できます。
今回は、介護・福祉業界における中途採用の現状や成功に導くためのポイントなどを、介護・福祉業界に特化した採用・人事コンサルタント監修のもとわかりやすく解説します。

【監修者】
太田 高貴
株式会社Blanket採用コンサルタント / 社会福祉士 / 一般社団法人総合経営管理協会 認定採用コンサルタント
成功事例もあわせてご紹介していますので、採用活動にぜひ役立ててください。
中途採用を検討する前に知っておくべき、介護業界の転職動向

中途採用で自社に合った人材を確保するためには、まず介護業界全体の転職状況を正しく把握しておくことが大切です。
ここでは、有効求人倍率や中途採用者の傾向など、採用計画を立てる上で役立つ基礎情報を解説します。
介護業界の有効求人倍率の推移
介護業界は、慢性的な人材不足が続いています。
厚生労働省の調査によると(※)、令和7年5月度の介護職の有効求人倍率は平均3.41倍でした。
「有効倍率3.41倍」は「1人の求職者に対して、3〜4件の求人がある」という状態です。このような売り手市場では、求人を出せば自然に人が集まるというわけにはいきません。介護現場で確実に人材を確保するためには、自社の課題を整理し、戦略的な求人設計を立てることが不可欠です。
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの入居施設だけでも、全国に2万施設以上あり、介護職を希望する人が少ないというよりは、「人手が必要な施設が多すぎる」といえます。
中途採用が約8割を占める理由
介護職の採用は、約8割(※)が中途採用とされています。
人手不足の介護現場では、未経験者の転職や高齢になってからの再就職も受け入れる傾向にあることが、中途採用が多い理由のひとつです。
一方で、新卒が介護職を希望するケースは他の職種と比べると少ないのが現状です。介護現場は「体力的な負担が大きい」「給料が安い」というイメージが根強くあります。
さらに、介護業界への関心の低さから、「そもそもよく知らない」「資格や勉強してきていないとできない」など、仕事として選択肢に入ってこないという事情が若年層の応募を妨げる一因となっていると考えられます。
※令和4年度 介護労働実態調査結果|公益財団法人 介護労働安定センター
転職者の多くが同業種出身
介護業界は未経験者の参入が目立つ一方で、実際には他業種と比べると同業種からの転職が非常に多いという特徴もあります。
マイナビが2024年に行った調査では、「医療・福祉・介護業界」への転職者のうち83.6%(※)が前職も同業種でした。
なぜ前職と同じ職種を選ぶ人が多いのでしょうか?その理由は、退職理由から見えてきます。
※マイナビ|転職活動における行動特性調査 2024年版マイナビ
中途転職者の主な退職理由
医療・福祉・介護業界で、退職理由としてよくあげられるのは、以下の項目です。
・仕事内容への不満
・給与が低い
・職場の人間関係が悪い
前職でのスキルや資格を活かすことで転職活動をスムーズに進められる点が、同業種を転職先として選ぶ理由のひとつと考えられます。
しかし、これらの退職理由を見てみると、仕事そのものに対してやりがい自体は感じていたものの、職場環境に課題を感じていたことも伺えます。
中途採用を成功させるためには、こうした背景を理解したうえで、「自社ならその課題をどう解決できるか」を明確に伝えることが大切です。
介護業界で中途採用を行うメリット
介護業界において中途採用は、単なる人材の補充だけでなく、現場にさまざまなメリットをもたらします。
主なメリットは次の4つです。
・基本的なビジネスマナーを身に着けているため、一から教育する必要がない
・同業種からの転職であれば即戦力を期待できる
・他業種からの転職であっても、前職で培ったコミュニケーション能力・スキルなどを活かすことができる
・他施設や他業種での経験をもとに、新しい視点や業務改善のヒントをもたらしてくれる
介護業界に関する中途採用は、現場の負担を減らすだけでなく、職場の環境を変えるきっかけとなることも期待できます。
失敗しない中途採用手法の選び方は?介護業界で使える3ステップ

中途採用を成功させるためには、自社の課題や予算などを踏まえて、適切な手法を選ぶことが大切です。
ここでは、中途採用活動を計画・実行するうえで押さえておきたい3つのステップをご紹介します。
ステップ1:自社の採用課題を見極める
まずは、今の採用活動で何が課題になっているかを明確にしましょう。
たとえば「応募数が少ない」のか、「応募はあるが定着しない」のかによって、取るべき施策は変わってきます。
・応募数が課題 → 求人掲載先の見直しや露出を増やす
・質や定着率が課題 → 求める人物が職場に希望する内容を把握する
応募数が基準に満たない場合は、より求職者の多い求人媒体に広告掲載を拡大し、求職者への露出を増やすことを検討したほうが良いでしょう。
理想とする人材が現れない場合は、その人材が求める職場環境を洗い出すことから始めてみましょう。自社に「理想像」とする職員がいる場合は、その人物から職場への要求や希望を聞いてみるのも良い方法です。そして、その人材に刺さると考えられる訴求を行うことが必要です。
また、採用した職員がすぐに辞めてしまう場合も同様に、希望に添えなかった部分に対して改善施策を実行することで定着率が高まります。加えて、採用段階でミスマッチが生じていないかどうかも確認し、根本的な課題解決を目指すことが重要です。
ステップ2:手法の特徴とコストを把握する
採用手法はさまざまですが、それぞれ特徴やコストが異なります。
| 手法 | 特徴 | コスト |
|---|---|---|
| 直接募集 | 自社サイトやSNSで募集詳細な情報を求職者へ提供できる。 | 自社でやる場合は無料(外注の場合は費用が発生) |
| 求人サイト | 求人情報をWebサイトに掲載する方法介護業界に特化している求人サイトを利用すればピンポイントでアピールできる | 有料(サイト・求人形態によって費用は異なる) |
| 人材紹介サービス | 自社のニーズに合わせた人材を紹介してもらえる採用工数を削減できる | 有料(成功報酬型が一般的) |
| リファラル採用 | 職員に知人や友人を紹介してもらう方法入職後のイメージがつきやすく離職率が低い | 組織による |
| ハローワーク | 厚生労働省が運営する職業紹介サービス無料で利用できる | 無料 |
それぞれの求人媒体の違いを正しく把握することで、自社に合った求人方法が見えてきます。
リファラル採用では、紹介フローを制度化して、紹介した従業員に対して紹介料を支払うケースも増えています。
採用手法の選び方や詳細をもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ステップ3:自社に合う組み合わせで運用設計する
採用手法はいくつもありますが、闇雲に選べばいいというわけではありません。自社に合った、持続可能かつ効果的な採用手法の設計が重要です。
たとえば「予算はギリギリだけどたくさんの人に応募してほしいから」という理由で求人サイトにいくつも求人を掲載したものの、思うような結果を得られず費用が無駄になるケースもあります。
一方で、「費用を抑えて募集をしたい」という理由でハローワークに求人を掲載したところ、自社が求める人材とは異なる求職者が多数現われ、対応に追われるということも少なくありません。
さらに、求人施策によっては、成果が出るまでに時間がかかるケースもあるため、計画的な設計が必要です。
職場に求める人物像や現状の職場環境、予算や求人計画に割ける人員などを考慮し、無理なく継続できる手法を選ぶことが、中途採用を成功に導くポイントです。
求職者タイプ別に見る中途採用手法の使い分け

中途採用では、求職者の経験の有無によって、適したアプローチや訴求内容が異なります。
ここでは、「経験者」と「未経験者・無資格者」に分けて、それぞれに合った採用手法の使い分け方を紹介します。
経験者向け:スキルの見極めと入職後ギャップの防止
経験者は即戦力として期待できますが、現場を広く理解していることから新たな職場により具体的な期待・希望を抱くため、「思い描いていた職場環境と違った」などのミスマッチが起きやすい層でもあります。
採用の段階で、仕事内容や職場環境を丁寧に伝え、入職後のギャップを防ぐことが大切です。
また、「介護経験あり」といっても、勤務していた施設やサービス形態によってスキルには差があります。たとえば、特別養護老人ホームで勤務経験がある方は、介護度の高い利用者へのケアの経験はありますが、デイサービスでのレクリエーションや在宅でのケアには戸惑う可能性が考えられます。
「どこで」「どのくらい」働いていたかをしっかり確認し、業務との相性を見極めることがポイントです。
職場環境を把握してもらうために、中途採用者向けの説明会や施設見学の実施などを、検討するのも良いでしょう。
未経験者・無資格者向け:不安を安心に変える採用アプローチ
未経験・無資格の求職者にとっては、「やっていけるかどうか」の不安が最大のハードルです。この層に対しては、自社の取り組みや姿勢を積極的に発信することが効果的です。
・資格取得支援制度や研修制度などの受け入れ体制を明示する
・実際に未経験から活躍している職員のインタビューや事例紹介を取り入れる
これらの施策は、介護職未経験者・無資格者に対して安心材料となります。しかし他の施設でも取り入れていることが多い内容のため、「自社ならでは」のポイントを、同時にアピールすることが大切です。
たとえば制度を導入した背景や、スタッフの成長を支援する想いなどは、差別化のポイントとなります。
職場の雰囲気をわかりやすく伝えるために、SNSで日常や施設の取り組みを継続的に発信することも有効です。
介護業界の中途採用を成功させる方法
中途採用を成功させるためには、単に求人を出すだけではなく、選ばれる施設になるための工夫が欠かせません。
ここでは、採用活動を進めるうえで意識したい3つのポイントをご紹介します。
自社の強みを把握する
まずは、自社の魅力や特徴を整理しましょう。福利厚生の充実度や職場の雰囲気、キャリアアップ支援など、思いつく内容をリストアップしてみてください。
ここで注意するべきポイントは「リストアップした内容を、自社が伝えたいように伝えることは避ける」という点です。
自社の強みに耳を傾け、目を通すのは求職者になります。そのため求職者の人物像をしっかり把握した上で、「どうすれば響くか?」を設計することが、応募者の獲得につながります。
たとえば「家庭と両立しやすい環境があります」という表現でも、具体的なシフト例や現場の声を添えることで、リアリティが増します。
求人原稿にこだわる
求人サイトや人材紹介サービスに掲載する求人原稿は、第一印象を決める重要なツールです。文章や写真など「どんな人に来てほしいか」を明確にしたうえで、細かい部分まで求職者の目線になり、作成することが求められます。
採用コンサルティングを活用する

「どこを改善すべきかわからない」「思うように応募が集まらない」と感じたときは、採用のプロの視点を取り入れることも有効です。
採用活動の見直しや課題の整理、運用設計などをプロにサポートしてもらうことで、自社に合った仕組みが明確になります。
自社だけで中途採用の求人計画を進めるのが難しいと感じたときは、採用支援の仕組みやコンサルティングサービスを活用することも、選択肢の一つです。
介護・福祉業界に特化したBlanketでは、採用課題の整理から、求人運用・媒体選定・原稿作成まで、現場のニーズに寄り添った伴走型の支援を行っています。
「採用を進めたいけれど、どこから手をつければいいか分からない」。そんなお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
成功事例から学ぶ!介護業界での中途採用事例
実際の介護業界における中途採用の成功事例を確認しておくことで、自社に取り入れるポイントや施策なども見えてきます。
ここでは、Blanketの支援によって中途採用に成功した実例を2件ご紹介します。どちらも柔軟な採用戦略により、人材確保を実現した事例です。
株式会社ゆず

地域密着で介護・医療・保育サービスを展開する株式会社ゆずでは、新施設の開設にあたり、「ゆずらしさ」を軸にした採用を重視。Blanketは、そんな想いを大切にしながら採用方針を設計し、理念に共感する人材をターゲットに設定しました。
説明会や特設ページで想いをていねいに伝え、候補者との対話の時間も設けるなどの工夫を凝らした採用計画を実現した結果、採用活動に不慣れな中でも、常勤介護職23名の採用に成功しました。
社会福祉法人ケアネット
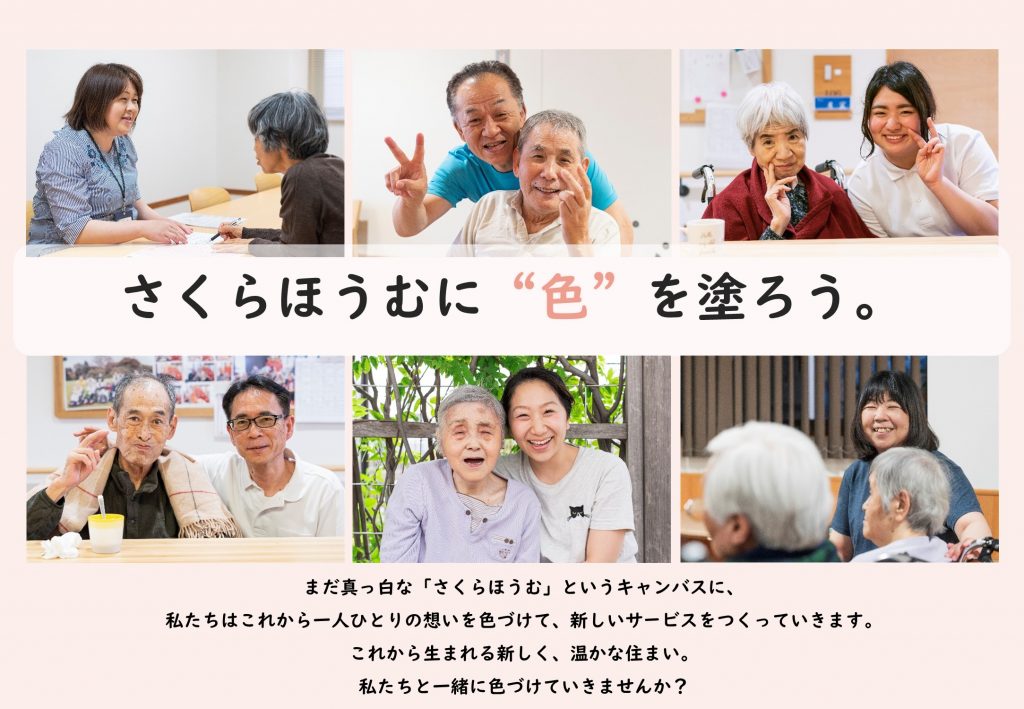
特別養護老人ホーム「さくらほうむ」の開設を目指したケアネットでは、当時、有効求人倍率8倍超の採用難地域で人材確保に臨みました。
Blanketは採用戦略の設計や特設サイトの制作に加え、継続的なミーティングで柔軟に支援。施設の「らしさ」を求職者に届ける方針を採用した結果、必要な人員を確保することができました。
まとめ
介護現場における中途採用は即戦力となるだけでなく、組織に新たな視点や活気をもたらす貴重な機会でもあります。しかし介護職の有効求人倍率は非常に高く、人材不足は業界全体の共通課題です。
そのような中で求める人材に出会うためには、自社の採用課題やリソース状況を踏まえたうえで、適切な採用手法を選び、戦略的に取り組むことが欠かせません。
リソース不足や改善点を見出すのが難しい場合は、外部の採用支援サービスを活用することもぜひご検討ください。
長く働ける人材と無理なく確実に出会うために、できるところから一歩ずつ進めていきましょう。







