介護・福祉業界の人材育成のカギとは?取り組み事例や成功の秘訣を徹底解説
公開日:2025/09/22 更新日:2025/11/17
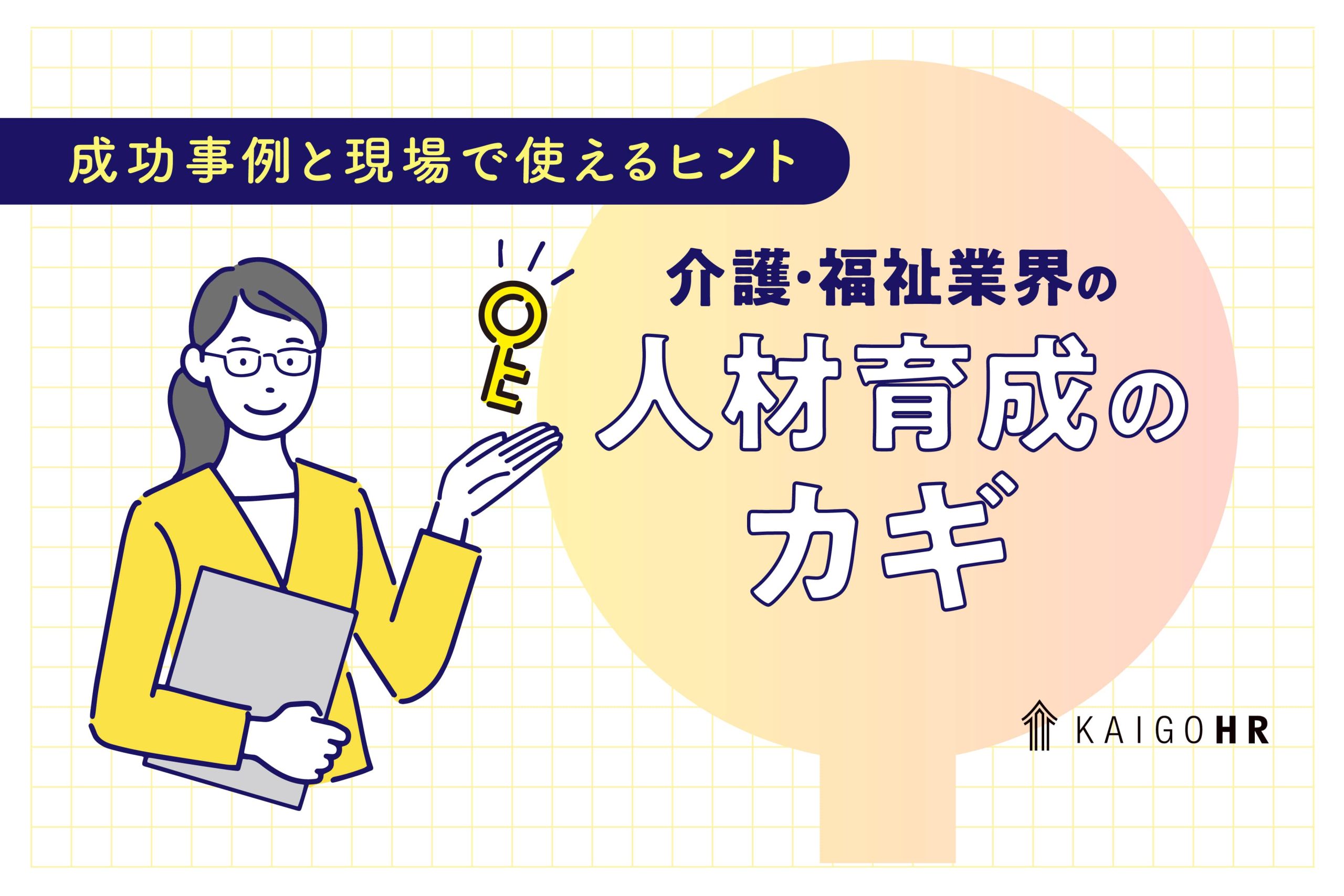
介護・福祉業界は慢性的な人材不足に直面しており、採用しても職員が定着しないという課題を多くの施設が抱えています。その課題解決には「採用」だけでなく、職員が長く働き続けられるよう支える「人材育成」の仕組みづくりが欠かせません。
そこで今回は、介護・福祉業界における人材育成の重要性や具体的な取り組み、成功している法人の特徴、さらに現場でよくある疑問への答えまで、介護・福祉業界の採用コンサルタントが幅広く解説します。
スキルアップと職場への順応、両方を支える育成のポイントを知り、組織の定着率向上につなげましょう。

【監修者】
野沢 悠介
株式会社Blanket取締役 / 人事コンサルタント / ワークショップデザイナー / 国家資格キャリアコンサルタント / Career Development Adviser
なぜ今、介護・福祉・福祉人材育成の取り組みが求められているのか

なぜ今、介護・福祉業界では人材育成の取り組みが重要視されているのでしょうか。介護・福祉業界の現状からおさらいしていきましょう。
介護・福祉業界における人材不足の現状
介護・福祉業界は長年、人材不足に悩まされ続けています。実際に介護・福祉職の有効求人倍率は令和7年7月の時点で3.88(※1)で、特に地方や小規模の事業所では人手不足が深刻です。
高齢化が進むなかで介護・福祉人材の需要は今後も増える見込みですが、その一方で離職率の高さも課題のひとつ。せっかく採用しても定着せず、結果として人材不足が解消されないという悪循環に陥っています。
人材「採用」だけでなく「育成」の必要性
介護・福祉業界では、採用しても早期に離職してしまうケースが多く、単に人を確保するだけでは人材不足の解決につながりません。そこで必要になるのが人材の「育成」です。
業務に必要なスキルを向上したり、安心して業務に取り組める環境を整えたり、職場でのキャリアパスを提示して自身の成長を描けるようにしたりなど、職場での定着率を上げるには、職員一人ひとりが現場で長く活躍できるようなサポートが重要になります。
意欲的な人材を採用できたにもかかわらず、職場に定着していない場合、受け入れ態勢が整っていないケースが多いです。
介護・福祉業界の人材育成の課題

このように介護・福祉業界では人材の育成が重要視されているものの、現場にはいくつかの共通した課題があります。ここでは特に多くの施設が直面しやすい3つの課題を紹介します。
人材争奪戦による人材の流動性の高さ
現在は社会全体で人材の獲得競争が激化している状況。採用した人材が他の職種にキャリアチェンジしたり、別の職場に転職してしまったりすることもよく起きます。
特に介護・福祉職は求人数が多く、他の施設や職種でも常に求人が出ているため、職員がより条件の良い職場へと移りやすい状況にあります。
結果として、せっかく新人教育や研修に力を入れても、職員が別の職場へ移動してしまい、育成の成果が組織に定着しにくいという課題が生まれています。
介護・福祉業界では法定研修を含め、研修自体は行われています。しかし、定着率を高めるという観点では“職場になじむためのサポート”が不足しているのが実情です。その結果、人材の流動性を抑えられないケースが多いのです。
OJT依存、体系的育成の欠如
介護・福祉現場では、実務を通じて学ぶOJT(On-the-Job Training)に頼るケースが多く見られます。しかし、OJT中心の育成では、担当者や先輩によって指導内容にばらつきが生じやすく、スキルや知識の標準化が難しいという課題があります。
その結果、職員が施設で求められるノウハウを十分に身につけられなかったり、教える側の方法が統一されず新人が混乱してしまったりすることも。
また、体系的な教育体制が整っていないと教える側の負担にもなり、新人だけでなくベテラン層の離職を招く原因にもつながります。
個人の裁量に任せるのではなく、マニュアルで「基準」を作ることが大切です。
多忙で研修に時間を割けない
介護・福祉現場は日々の業務が非常に忙しく、職員が研修や学習の時間を確保することが難しいというのも課題のひとつ。せっかく人材育成の仕組みを作っても、形式的に終わってしまうケースが少なくありません。
結果として、計画的なスキルアップやキャリア形成が進まず、育成の効果が十分に発揮されないことがあります。現場の忙しさと人材育成のバランスをどう取るかが、多くの施設にとって大きな課題となっています。
人材の定着率を高めるには、新人が「職場になじむ」ためのサポートがあることが重要です。業務に必要な知識・技術の習得に加え「+α」の部分がカギになります。しかし、法定研修だけでもボリュームが多く、「+α」の部分まで手が回らないというケースが多いです。
介護・福祉事業所の人材育成+αで実施するポイント

職場定着率を高めるには、業務において必要なスキルの育成だけでなく、職場に馴染む「+α」の取り組みも同時に行っていくことが大切。そこで次は、具体的にどのような取り組みを行えば良いのか、5つのポイントを紹介します。
キャリアパス制度の導入でモチベーション向上
まずは、職員のモチベーションを高める制度を導入すること。介護・福祉現場で特に意欲的な職員のモチベーションを高めるには、明確なキャリアパス制度の導入が効果的です。
昇格や資格取得に応じてステップアップできる仕組みを整えることで、職員は自分の将来像を具体的に描きやすくなります。また、目標を持って働くことができると、「この職場で成長していける」という安心感にもつながります。
eラーニング・ICTの活用で効率的な研修
日々の業務で忙しい介護・福祉職員にとって、効率的に学べる仕組みは欠かせません。eラーニングやICTを活用したオンライン研修を導入し、スキマ時間に学習できる体制を整えると良いでしょう。
スマートフォンやタブレットからアクセスできる手軽さだけでなく、教材の更新や共有が簡単なのもオンライン研修のメリット。動画やクイズ形式など多様なコンテンツを取り入れることで理解を深めたり、学習意欲を維持したりする効果もあります。
さらに、OJT研修だけに頼らない研修システムを取り入れることは、教える側の現場の負担を軽減にもなります。
外国人材向け教育・多文化共生研修
介護・福祉現場では外国人職員の採用が増加しています。外国人職員の育成においては、言語や文化の違いに配慮した研修を実施することが必要不可欠です。
例えば、介護・福祉専門用語を分かりやすく学べる教材を用意したり、日本の生活習慣に関するオリエンテーションを定期的に開催したりなど。スキルの習得だけでなく、生活環境を整えるサポートが大切です。
また、日本人職員側に対しても異文化理解を深める研修もポイント。日本人と外国人、それぞれがお互いの理解を深める研修を取り入れることで、コミュニケーションが円滑に取れるようになり、外国人材の定着率を高めるだけでなくチームワークの強化ができるでしょう。
メンター制度とメンタルサポートの充実
新人や若手職員が安心して働き続ける環境を作るためには、メンター制度の導入が効果的です。介護・福祉現場に限らず、職場での“ちょっとした悩み”を相談できずに孤立してしまう新人や若手職員は少なくありません。
業務上の質問はできても、職場でのルールなどを質問できず、働きにくさを覚えたり職場に馴染めなかったりすることもあるはずです。そんなとき、経験豊富な先輩職員など気軽に相談できる存在がいれば、孤立を防ぎ、早期離職の防止にもつながります。
また、介護・福祉現場は心身の負担が大きいため、メンタルヘルス対策も欠かせません。定期的なメンタルケア研修や外部相談窓口の設置は、職員の安心感を高める有効な施策です。育成とメンタルサポートを両立させることで、働きやすい職場環境を作ることができるでしょう。
支援策を活用した研修費用・時間の軽減
人材育成においてスキルを高める研修は必要不可欠。しかし、実際のところ、研修費用や時間の確保が大きな課題となります。そこで活用したいのが、国や自治体の支援策です。
例えば、「介護人材確保・職場環境改善等事業」や「人材育成支援事業」などを利用すれば、研修費用や外部講師のコストを抑えることができます。
同時に、参加する職員の時間的負担を軽減する取り組みも行いましょう。せっかくプログラムを組んでも、職員が参加できないと意味がありません。勤務時間内に研修を組み込んだり、シフトを工夫したり、職員が無理なく参加できる工夫が必要です。
施設側の経済的負担、職員側の時間的な負担を軽減しながら研修を行える体制づくりがポイントとなります。
介護・福祉業界の人材育成に成功している法人の特徴

次は、実際に人材育成に成功している法人の特徴を見ていきましょう。
理念を重視した「理念実現のための組織づくり」
介護・福祉業界で人材育成に成功している法人の多くは、まず「理念」を出発点にしています。
給与や休日といった条件面を整えるだけでは、「働きやすさ」は向上するものの、「働きがい」といったモチベーションの向上にはならず、離職防止や成長促進につながりきらない離職防止や成長促進につながらない場合が多いため、組織として「どう在りたいのか」「何を目指すのか」を明確にし、それを職員と共有することが欠かせません。
理念に共感できる職員が集まり、その人たちが「働きやすい」「働き続けたい」と感じられる環境を整える。こうした組織づくりができている法人では、職員の成長意欲も高まり、人材育成の取り組みが自然と根づいていきます。
研修を現場に浸透させる仕組みがある
新人研修でよくあるパターンが、知識や技術を伝えた時点で「完了」と研修を終わらせてしまうこと。しかし、研修の目的は“実際に学んだ内容を使えるようになること”です。
人材育成に成功している法人は、研修後にメンターや上司がフォローを行い、日々の業務の中で知識をどう使うかを一緒に確認するなど、研修内容を現場で継続的に活かせる仕組みづくりを備えています。
また、学んだ内容を職員同士で共有する機会を設け、チーム全体に浸透させている法人も。このように、研修を学びの場として終わらせず現場に順応させる仕組みがあると、研修の効果も高まります。スキルアップを実感しやすくなり、職員の定着率向上にもつながるでしょう。
職員の成長が見える評価・フィードバック制度
もう一つの成功要因は、職員の成長を「見える化」する評価とフィードバックの仕組みです。単にできる・できないを判定するのではなく、成長の過程を段階的に評価し、具体的な改善点や良かった点をフィードバックすると、職員のモチベーションも高まります。
また、評価内容をキャリアパスや昇格に結びつけることで、努力が正当に認められる実感を持てるのもポイントです。成長が見えることで職員は自己効力感を得やすくなり、さらに学ぼう・続けようという意欲につながります。
組織や仕事環境に順応できるバックアップ体制があってこそ、「研修」や「育成」の効果が現れます。
介護・福祉業界における人材育成の取り組みでよくある疑問

人材育成を進めるなかで、介護・福祉事業所の現場からは共通した悩みや疑問が多く聞かれます。ここでは特に相談の多い「新人の離職率」と「管理職層の育成」について、具体的な解決のヒントを紹介します。
新人の離職率を下げるにはどうすればいい?
若手職員の早期離職は、多くの介護・福祉施設が直面している大きな課題です。
多くの事業所では研修でスキル習得のサポートを行っていますが、「職場にどう馴染むか」という視点が抜け落ちているケースが少なくありません。
職場への定着率を高めるうえで大切なのは、知識や技術の習得と同時に職員が組織に順応できるよう支援すること。スキル研修に加えて職場社会化の仕組みを整えることで、新人の定着率は大きく改善します。
また、チーム内での役割体験を通して「自分はここに必要とされている」という感覚を持ってもらうことも効果的です。メンター制度による日常的なサポートなど、今回紹介した研修ポイントを取り入れてみてください。
管理職層が不足しています。中堅職員を育成するにはどうすればいい?
介護・福祉業界だけでなく多くの業界で共通する課題が「管理職層の育成」です。専門職としてのスキルが高くても、組織運営やチームマネジメントに必要な経験が不足している場合、リーダーになった際に大きな壁に直面しやすくなり、離職につながることもあります。
解決のカギは、管理職に就く前の段階から少しずつリーダー業務を経験させることです。例えば、小規模なプロジェクトを任せる、後輩指導を担当してもらうなど。段階的に役割を広げていくことが効果的です。
実務を通して組織運営の視点を身につけることで、中堅職員が将来の管理職候補として育ちやすくなります。
組織や仕事環境マネジメントは「何年も現場で働けば自然とできるようになる」ものではありません。専門スキルと管理職に必要なスキルは別モノ。マネージャーに必要なスキルは日々の専門職の業務だけでは学びきれないものも多いので、リーダー層になる前から少しずつチーム運営の経験を積ませることが大切です。
Blanket では、施設ごとの課題や強みに合わせた具体的な改善施策を提案し、現場とともに人材育成を進めてきました。
人材育成の取り組みは、その事業所の課題を踏まえて進めることが欠かせません。もし「人材育成が思うように進まない」「定着につながる仕組みをつくりたい」といったお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
まとめ
介護・福祉業界では慢性的な人材不足が続き、採用だけでは課題解決が難しい状況にあります。そのため、職員をいかに定着させ、長期的に活躍できるよう育成していくかが大きなカギとなります。
ここで重要なのは、育成を「スキルや知識の向上」だけに限定しないことです。新人や中堅職員が職場に順応し、組織の一員として安心して働き続けられるよう支援することも、人材育成の大切な一部です。
メンター制度やキャリアパスの提示、研修制度の整備に加え、メンタルサポートや職場環境改善といった「+α」の取り組みを組み合わせ、職員の成長と定着を高めましょう。







