訪問介護の人材育成を研修で加速!忙しい現場でもスキルアップと定着を実現
公開日:2025/10/08 更新日:2025/11/13
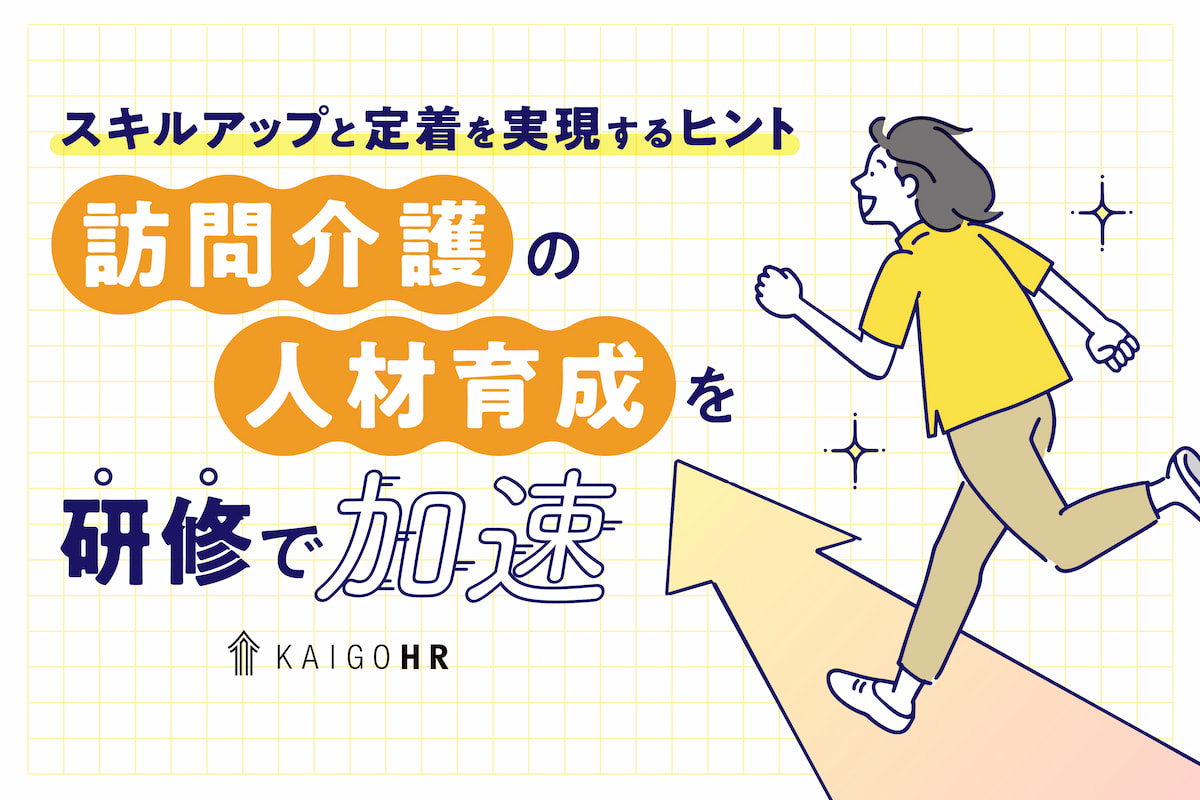
高齢化が進む中で、在宅での暮らしを支える「訪問介護」は、地域包括ケアの要となるサービスです。しかし現場では、職員の高齢化や人材の確保、新人の早期退職といった課題が課題が浮き彫りになっています。結果として、安定したサービス提供が難しくなるなど、利用者の安心感や満足度にも影響が及ぶのが現状です。
だからこそ、職員一人ひとりが安心して働き続けられる仕組みづくりや、スキルアップを後押しする人材育成が欠かせません。とはいえ、訪問介護事業所の多くは小規模で、体系的な研修プログラムを自前で整えるのは難しいですよね。
そこで注目されるのが、OJTを基盤とした育成の工夫や、外部研修・最新支援策の活用です。今回は、介護・福祉業界の人事コンサルタント監修のもと、訪問介護における人材育成を「こなす研修」から「人が育つ研修」へと変えるヒントを、具体的な方法とともに解説します。

【監修者】
野沢 悠介
株式会社Blanket取締役 / 人事コンサルタント / ワークショップデザイナー / 国家資格キャリアコンサルタント / Career Development Adviser
訪問介護の人材育成における主な課題と構造

訪問介護は、要介護者の生活を支える重要なサービスです。しかし、現場には「人材が育ちにくい」構造的な課題があります。
ここでは特に多くの事業所が直面する3つの課題を整理し、なぜ人材育成がその解決につながるのかを解説します。
小規模事業所での人材育成の難しさ
訪問介護事業所の多くは職員数10名以下かつ職員は、非常勤(パート)が多い傾向にあります。直行直帰の働き方が一般的なため、研修機会を確保できない傾向にあります。
加えて、利用者ごとに必要とされるケアは大きく異なり、画一的なマニュアル化が難しいのが実情です。そのうえ職員の入れ替わりも少なくなく、経験やノウハウの共有が十分に行われないまま現場に立たざるを得ないケースもあります。結果として、研修を自前で整えることは難しく、人材を計画的かつ継続的に育てる体制を築きにくい状況です。
定着には法定研修だけでは不十分
訪問介護員は、虐待防止や感染症対策など法定研修を受講することが義務づけられています。
しかし、多くの事業所ではeラーニングや外部研修で基礎知識を補っているものの、それだけでは現場力の向上や長期的な定着には結びつかないという課題を抱えています。
人材の定着率を高めるには、新人が「職場になじむ」ためのサポートや、職員が業務や組織に感じている課題を解決するための仕組みづくりがカギになります。
ICT活用における高齢職員への対応
厚生労働省が令和5年に発表した資料によると、訪問介護員の平均年齢は54.4歳、そのうち65歳以上は24.4%を占めています(※1)。
業務効率化や記録の標準化を目的にICT機器の導入が進んでいますが、高齢職員の中にはタブレットやアプリに苦手意識を持つ人も多く、導入効果を十分に発揮できないケースがあります。
このため、人材育成の観点では、高齢職員にも使いやすいツールやサポート体制を整えることが重要です。
※1 新しい複合型サービス(地域包括ケアシステムの深化・推進)|厚生労働省
訪問介護の人材育成を成功させる「研修+α」の具体策

訪問介護業務に必要な知識・スキルを向上させられること、そして「この職場で働き続けたい」と思える環境をつくることが、人材定着とサービス品質の両立につながります。ここでは、訪問介護事業所が実践しやすい5つの具体策を紹介します。
外部研修の活用
小規模な訪問介護事業所では、予算やシフト調整などの都合から、社内で体系的な研修を整備することが難しい場合が多くあります。そこで有効なのが、自治体や社会福祉協議会などが提供する外部研修の活用です。
外部研修では、介護の基礎知識や最新のケア手法、法定研修の内容などを効率的に学ぶことができ、職員全体のスキル底上げにもつながります。
事業所側は、こうした基礎部分を外部に任せることで、OJTや個別フォローなど、現場での指導やサポートにより多くのリソースを割けるのもメリット。結果として、職員一人ひとりが安心して実践力を高められる環境を整えやすくなります。
OJTの仕組み化
訪問介護は個別性の高いケアが多いため、現場での学びが重要です。ただし、先輩職員の裁量に任せすぎるOJTは、教える内容に差が出てしまったり、新人職員にとっては難しい内容になってしまったりという課題があります。
そこで重要なのがOJTの仕組み化です。チェックシートやマニュアルを用意し、同行研修の流れを標準化しましょう。
さらに、事例共有の仕組みを整えることも有効です。訪問介護では、作業内容が決まっていても利用者ごとに住んでいる環境が異なるため、予期せぬ出来事が起こり得ます。実際の事例を共有することで、「こういうときはこんな対応ができるのか」とOJT以外でも学びのチャンスにつながります。
職場環境の工夫
訪問介護は直行直帰が多く、職員同士の交流が少ないため孤立感を抱きやすい傾向にあります。仕事上の疑問点は質問できても、「相談するほどでもないけれど……」という小さな悩みを抱えている職員も多いでしょう。
職員の孤立感を解消するには、コミュニケーションの機会を増やすことが大切。研修もその方法のひとつとなり得ますが、忙しい中で研修ばかり増やすのは現実的ではありませんよね。
おすすめは、定期的に面談の機会を設けたり、メンター制度を作ったり、職員の抱える悩みをヒアリングする体制を整えること。そして、“OJT担当者”以外の職員とも関わりを持てる体制を作りましょう。「現場から事業所に帰るのは負担」という場合には、オンラインで相談できる体制を整えるのもひとつの手です。
ある事業所では、事務所に戻ったら昼食が取れるよう冷凍食品を常備したことで、自然と職員が顔を合わせる機会が増えたというケースもあります。小さな仕掛けでも「戻ってきたくなる職場」は定着率に大きな効果をもたらします。
ICTの活用による効率化・学習支援
やはり、業務効率化にはICTを活用するのが有効です。オンライン研修や動画教材を活用すれば、職員が事業所に集合できなかったとしても、時間や場所に縛られずに学習機会を確保できます。
また、記録アプリを取り入れたりオンラインで事例を確認できたり、「現場で必要なときにすぐに記入・確認」体制を整えれば、情報共有のスピードアップにもつながります。
とはいえ、高齢職員のなかには、ICT導入に対して不安を覚える人もいるでしょう。そこで重要なのが、「導入して完結」するのではなく、ICT操作を人材育成の一環として丁寧にサポートすること。ICTが「負担」ではなく「助け」になるよう位置づけることで、世代を問わず働きやすい環境が整います。
ICTによる効率化や人材育成を進めるために、「ICT技術を使うことに抵抗がないか」「新しいツールや仕組みにも前向きに取り組んでいるか」ということを採用基準にして、選考時に確認するのも良いと思います。
採用・定着につながる戦略的育成と仕組みづくり
研修は「人材を育てる」だけでなく「採用の魅力づけ」にも直結します。たとえば、研修制度を採用ページや求人情報で積極的に発信することで、「安心して働ける職場」という印象を与えられるでしょう。
さらに、紹介制度を導入したり、地域の福祉団体との連携を進めたりして、安定的な人材確保を目指すことも大切。入社前からコミュニケーションをとっていれば、採用のミスマッチも起きにくく、職員も定着しやすくなります。
キャリア段階に応じた介護職員の人材育成方法

人材を育てるときには、本人の習熟レベルに合った研修プログラムを実施することが大切です。ここでは、キャリア段階に応じた訪問介護職員の人材育成のポイントを解説します。
初心者(新人・未経験者)向け研修
初心者の場合は、基本知識の習得、利用者と関わる際のマナーを重点的に学ぶ内容が良いでしょう。この初期研修が、その後の即戦力化と離職防止のカギになります。
- 基本介助スキル(食事・入浴・排泄介助など)
- 利用者宅での接遇マナー(清潔感、言葉遣い、プライバシーの配慮など)
- 訪問介護記録の書き方
- 緊急対応の基礎(転倒・体調不良時の初期対応など)
- OJT+メンター制度で安心感を持たせる
訪問介護は利用者宅という個別性の高い環境で行われるため、利用者ごとに「配慮が求められるポイント」が異なります。
そこで重要なのがOJTです。これらをOJTの中で共有しておくことで、新人職員が無意識に不適切な対応をしてしまうリスクを減らし、利用者との信頼関係を円滑に築くことができます。
OJTでは利用者との関わり方をしっかり伝えましょう。また、OJTの内容を伝達側個人の裁量に委ねず、「このタイミングでは、ここまでを習得してもらう」と学習内容や到達基準を作っておくことも重要です。
中級者(経験2〜5年程度)向け研修
初心者レベルが習得できたら、応用的なスキルを学び、チームの一員として役割を担えるようになる時期です。スキルを深めること、そして次期指導者の育成につながる経験を増やしていきましょう。
- ケースカンファレンス、事例検討会の参加
- ICTツールの活用研修(記録アプリ・オンライン連絡)
- 後輩指導の基礎(OJTでの声かけ、簡単なフィードバック)
- メンターとしての後輩サポート
中級者になると、新しい知識を増やしつつ、OJTやメンター制度などで後輩を育成する段階に入ります。そこで大切なのがコミュニケーションスキル。チームを円滑に運営するための立ち回り方法などが身に付く研修も取り入れていきましょう。
例えば「認知症ケア」を例にとると、初診でも認知症の基礎的な理解は必要ですが、中堅はそれに加えて「それぞれの利用者の個性を尊重しながら最適なケアを選択できる」応用力を高めることが望ましいなど、業務に必要な専門性の引き出しを増やしていく段階といえます。
管理者・リーダー層向け研修
管理者やリーダー層に求められるのは、現場の業務スキルに加えてマネジメント力とリーダーシップの強化です。シフト調整やクレーム対応、部下の育成や評価方法など、組織運営に直結する分野を重点的に学ぶ研修を取り入れましょう。
- マネジメント研修(シフト調整・業務管理・苦情対応など)
- 指導者研修(人材育成の進め方、効果的なフィードバック手法)
- チームマネジメント・リーダーシップ養成
- 多職種協働研修(医師・看護師・ケアマネジャーとの連携強化)
- 経営改善やICT導入支援に関する知識習得
専門職として高いスキルを持っているからといって、必ずしもマネジメント力が備わっているわけではありません。
マネジメントスキルと専門職のスキルは別物であるため、せっかく育ったリーダー層を離職させないためにも、段階的に裁量を持たせて経験を積み、管理力を育てていくことが重要です。
研修を現場に浸透させる3つのポイント

研修を実施するだけでは、人材育成の効果は十分に発揮されません。重要なのは、現場で学んだ知識やスキルを日々の業務に定着させることです。
ここでは、介護・福祉業界の人事コンサルである野沢がこれまでに培った経験をもとに、研修を現場に根付かせ、成果を最大化するための3つのポイントを紹介します。
支援策を活用した研修対策
訪問介護事業所は小規模で人手が限られることが多く、研修を自前で行うには時間やコストの負担が大きくなります。その場合は、国や自治体の補助制度や助成金を活用することが有効です。
研修費用の助成や、代替職員確保の費用補助など、自治体によりさまざまな支援を行っているため、それらを活用することで、費用面の負担を軽減しつつ職員のスキル向上を図れます。
職員にとっても、スキルを身につけたり同業者や地域の人との関わりを持ったりすることができ、事業所は経営的な負担を抑えながら、体系的な研修を実施できる環境を整えられます。
忙しい職員でも参加しやすい環境づくり
先述のとおり、訪問介護の職員は直行直帰やシフト勤務が多く、研修参加のハードルが高いのが実情です。そのため、シフト調整を工夫したり、オンライン研修やeラーニングを導入したりすることで、忙しい職員が無理なく学べる環境をつくりましょう。
まとまった時間が取れない場合は、短時間で実践的な内容を学べる研修にしたり、オンライン・オフラインでの事例共有会から始めたりするのもおすすめです。
「前回の研修は役に立った」と実感してもらうことで、研修への心理的ハードルが下がり、参加意欲が高まります。特に、オフラインなら職員が事業所に足を運ぶ必要もなく、現場負担を抑えつつ、学習環境を作ることができます。
研修の成果を活かす仕組みづくり
研修で学んだ知識やスキルを現場で活かす仕組みを作ることが、育成効果を最大化するポイント。研修内容をキャリア評価や人事考課に反映したり、業務改善やサービス向上の場で実践できる機会を設けましょう。
また、定期的な振り返りや事例共有の場を設けることも有効です。研修内容が個人だけでなく組織全体の成長につながります。これらの仕組みを作ることで、研修が単なる「学び」で終わらず、現場の成果につながる「育成施策」として定着していくことが期待できます。
訪問介護の人材育成で研修を活用している事例
研修の重要性は理解していても、「活用できるか」はまた別問題です。「どうやって新人を研修していけばいいか」「職員にマネジメント力を身につけてもらうにはどうしたらいいか」が見えずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
もし、マネジメントやコミュニケーションの研修を取り入れたいと考えているのなら、ぜひBlanketにご相談ください。管理者向けのマネジメント・コミュニケーション研修を用意しています。
実際にBlanketのマネジメント研修を導入した社会福祉法人福祉楽団では、参加者から「部下との関わり方を改めて考えられた」「チームマネジメントが日々のケア業務に直結していると実感できた」といった前向きな声が寄せられ、職場全体の安定と活性化につながりました。
Blanketでは、管理者向け研修のほかにも、職員の基礎スキル研修やOJT支援などさまざまな研修プログラムの提供や、研修育成体制構築のためのコンサルティングなどを実施しています。
現場の課題や目指す方向性に合わせて最適なプランをご提案できますので、研修・人材育成体系の構築の課題や悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
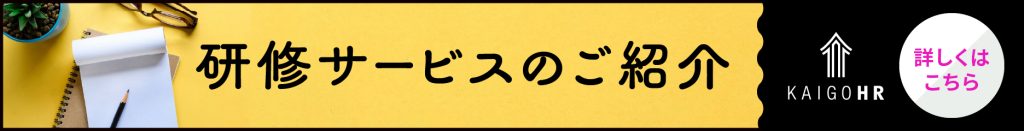
まとめ
訪問介護では、職員一人ひとりのスキルと現場対応力が、利用者の安心・安全な生活に直結します。サービスの質を上げるためにも、研修を通して職員のスキルアップを図りましょう。
研修のためのまとまった時間が取れないという場合は、OJTや外部研修、ICT活用をして、効率的に学べる環境を整えたり、「職員の多忙さ」を解消する施策を取り入れるのが有効です。
また、研修は人材定着の面でも非常に重要。「研修が充実している」「この職場には気軽に相談できる環境がある」と職員に安心感を覚えてもらうことが、職員の早期離職防止につながります。







