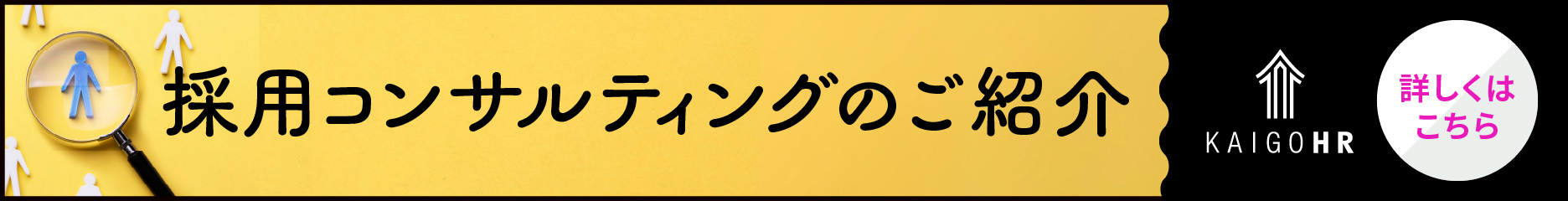ストレスチェック義務化が中小にも拡大へ。「小規模事業場版マニュアル」から考える介護・福祉職のメンタルヘルス支援
公開日:2025/10/27 更新日:2025/11/06

介護・福祉の人事・組織づくりを支援するコンサルタント・太田が、話題のニュースやトレンドから、現場で役立つヒントを読み解く連載コラム。今回の“ひとさじ”は、ストレスチェック義務化をきっかけに考える、介護・福祉職のメンタルヘルス支援です。
ストレスチェック義務化の対象が拡大
厚生労働省は、ストレスチェック制度の実施に関する「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に向けたワーキンググループを立ち上げました。2025年10月に行われた初会合では、これまで50人以上の事業場を前提としていた現行マニュアルを見直し、50人未満の小規模事業場でも実施しやすい仕組みを整備する方針が示されています。
背景には、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法があります。改正法では、公布から3年以内に常用労働者50人未満の事業場にも、ストレスチェックと高ストレス者への面接指導の実施が義務づけられます。これにより、介護・福祉業界を含む多くの中小法人が、メンタルヘルス対策をより計画的に進める必要が出てきました。
ストレスチェックは、職員が自分の心身の状態を客観的に把握し、必要に応じて支援を受けられるようにする仕組みです。義務化の対象が広がることは、法律対応という枠を超え、すべての働く人の健康を守る体制づくりの一環といえます。
なぜ「小規模事業場版」が必要なのか
ストレスチェック制度は2015年に始まり、これまで主に大企業や自治体など大規模事業場を中心に運用されてきました。しかし介護や福祉の分野では、職員数が数十人規模の事業所が多く、限られた人員で業務をこなす職場が少なくありません。事務職がいない、産業医がいない、外部相談窓口が整っていないなど、実施したくても手立てがないという現場の声もあります。
また、小規模事業所では、管理者や職員同士の距離が近く、プライバシーの確保が難しい点も課題です。「誰のストレスが高いと判定されたのか」「結果が職場に知られてしまうのでは」といった不安が制度への抵抗感につながることもあります。新マニュアルでは、こうした事情を踏まえ、外部機関との連携や実施体制の工夫を盛り込み、プライバシーを守りながら現実的に実施できる方法を整理する方針です。
厚労省が提示した資料には「小規模事業場の取組事例」も紹介されています。商店街の事業者が合同で実施したり、医療法人が地域の小規模施設と共同で体制を整えたりといった例もあり、業種や規模に応じた柔軟な工夫が広がりつつあります。こうした動きは、介護・福祉業界にとっても大いに参考になります。
介護・福祉現場で求められるストレス対策の視点
介護・福祉の職場は、人と人との関わりを軸に成り立ち、やりがいと同時にストレスを抱えやすい環境です。身体的な負担に加え、利用者や家族への対応、職員同士の調整など、精神的な疲れが積み重なりやすい構造があります。
こうした現場にこそ、ストレスチェックを職員の声を拾う仕組みとして生かす視点が求められます。形式的に実施するだけではなく、結果をどう現場づくりにつなげるかがポイントです。
特に介護現場では、次のような工夫が効果的です。
外部支援機関との連携を図る
小規模法人では、産業医や保健師が常駐していないケースも多いため、外部のメンタルヘルス支援サービスを検討するとよいです。具体的には、民間の従業員支援プログラム(EAP:Employee Assistance Program)を契約したり、地域産業保健センターを活用したりする方法があります。
管理職へのサポートを強化する
管理者やリーダーが「相談を受ける側」として抱えるストレスも見逃せません。職員の声を受け止めながら、自身も業務とマネジメントの板挟みになりやすいため、セルフケア研修やメンタルヘルス研修を併せて実施します。
職員が気軽に話せる仕組みをつくる
定期的な1on1ミーティングや匿名の相談フォームなど、日常的にストレスを共有できる仕組みを整えます。家庭や介護との両立、職場の人間関係など、一人で抱え込みやすいテーマこそ、早期に声を上げられる環境づくりが重要です。
ストレスチェック結果を職場づくりに生かす
個人の結果を集計し、全体の傾向を把握して課題を共有します。「忙しい時期に業務が集中している」「夜勤後のケアが足りない」など、改善のヒントが見つかることもあります。数値で終わらせず、働きやすさを高めるための材料として対話を重ねることが大切です。
こうした取り組みを積み重ねることで、ストレスチェック制度が単なる法対応ではなく、現場の声を活かした職場改善の仕組みになります。
小さく始めて、続けることが鍵
小規模事業所にとって、ストレスチェックの導入は負担に感じられるかもしれません。人手も限られ、紙の配布や集計などの事務作業だけでも手間がかかります。それでも、外部支援を活用したり、無料のオンラインツールや自治体提供の様式を使ったりすれば、無理なく始められます。重要なのは完璧にやることではなく、職員の声を継続的に拾うことです。
一度きりの実施では意味がなく、毎年少しずつでも振り返りを重ねることで、職場の課題や変化が見えてきます。チェック結果をきっかけに「どんなことがストレスになっているか」「どうすれば働きやすくなるか」を話し合うことが、信頼関係を育てる第一歩になります。
介護・福祉の仕事は、人の心に寄り添う仕事です。だからこそ、働く人自身の心のケアを制度として支える仕組みが欠かせません。厚労省が進める「小規模事業場向けマニュアル」は、法律対応だけでなく、現場が無理なく実践できる方法を考えるヒントになると思います。小さくても始めてみること、そして続けていくことが、職員の健康とチームの安定を守る一歩になるのではないでしょうか。
参考:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第1回会合」