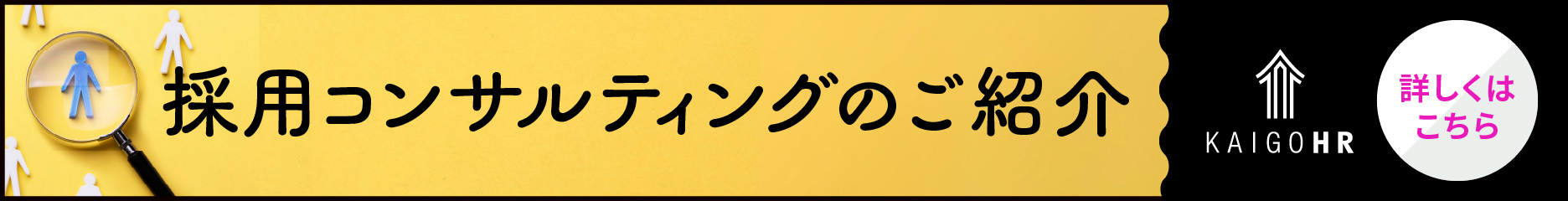介護・福祉業界の人手不足の現状は?取り組みから学ぶ、現場で使える解決策
公開日:2025/11/07 更新日:2025/11/13
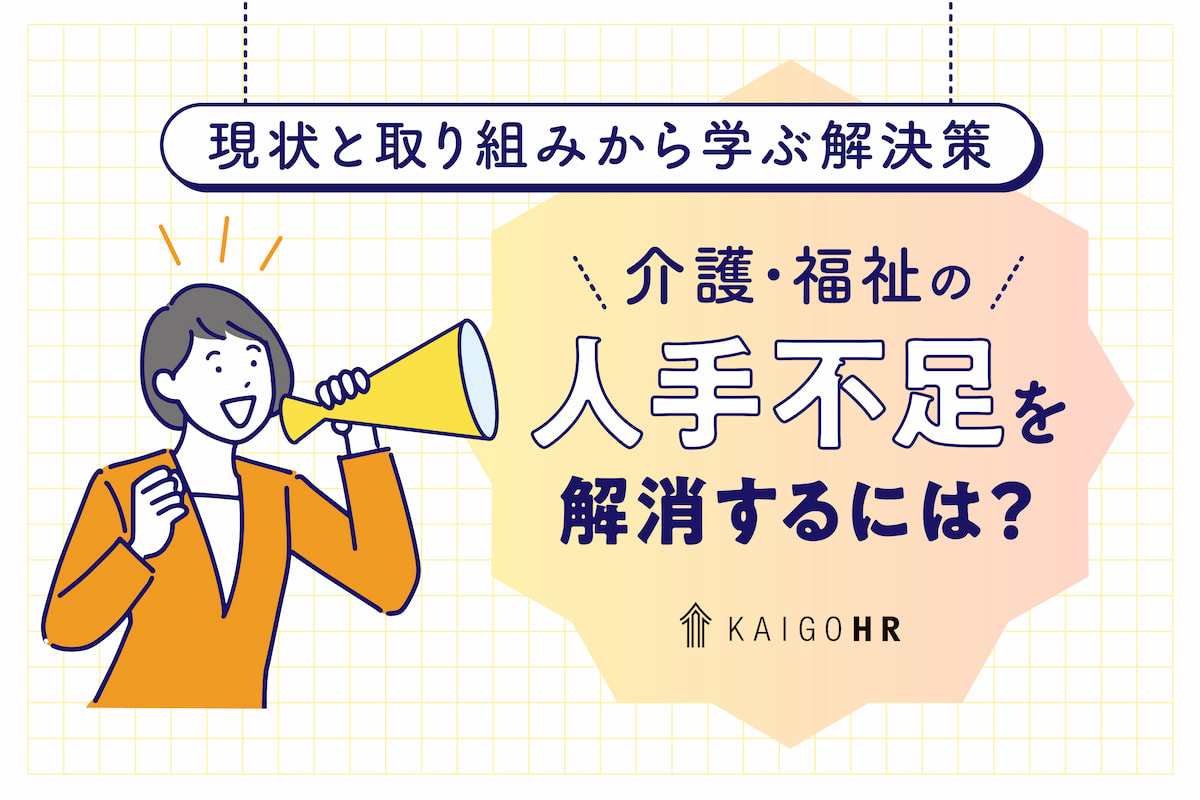
介護・福祉施設の運営で頭を悩ませる大きな課題のひとつが、人手不足です。慢性的な労働力不足や給与や待遇面の課題など、さまざまな要因が重なり、採用や現場運営に影響を与えています。
しかし、少しの工夫や仕組みづくりで、採用率や職員の定着率を大きく改善することも可能です。
今回は、介護・福祉業界の採用・人事コンサルタント監修のもと、実際に成果を上げた現場の事例をもとに、人手不足解消に向けすぐに取り入れられる解決策をご紹介します。

【監修者】
太田 高貴
株式会社Blanket採用コンサルタント / 社会福祉士 / 一般社団法人総合経営管理協会 認定採用コンサルタント
介護・福祉業界の人手不足はどのくらい深刻か?現状と統計データ

介護・福祉業界では、慢性的な人手不足が続いています。高齢化とともに介護・福祉サービスの需要が急速に拡大する一方で、担い手の確保が追いつかない状況です。
厚生労働省の統計でも、有効求人倍率・地域格差など、あらゆる指標が人材不足の深刻さを示しています。ここでは最新データをもとに、介護職の人手不足の実態を整理します。
介護職の有効求人倍率・就業者数の推移
厚生労働省の最新データによると、介護職の有効求人倍率は3.94倍と、全産業平均(1.20倍)を大きく上回っています(※1)。これは求職者1人に対して約4つの求人がある計算で、圧倒的な売り手市場といえます。
また、就業者数は2024年に初めて減少(※2)。需要の伸びに追いつかず、今後も深刻な人材不足が懸念されます。
それに対して、訪問介護員や介護職員を合わせた2職種の離職率は12.4%(※3)。全産業の平均以下で改善傾向にあるものの、就労者の定着に向けた対策は必須です。
※1 一般職業紹介状況(令和7年8月分)について|厚生労働省
※2 介護人材確保の現状について/都道府県別有効求人倍率(令和7年3月)と地域別の高齢化の状況|厚生労働省
※3 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について|公益財団法人介護労働安定センター
地域や施設規模による人手不足の差
介護分野の有効求人倍率といっても、詳細は地域ごとに大きく異なります。高齢化のスピードや人口構成が地域ごとに違うため、必要な就労者数にも差が生じているためです。
たとえば厚生労働省がまとめた令和7年3月の介護人材確保の現状によると、東京都では、75歳以上の人口が2015年の146.9万人から2025年には194.6万人へと約1.33倍に増加(※)。それに伴い、介護職の有効求人倍率は7.65倍という極めて高い水準に達しています。
一方で、75歳以上人口は、都市部では急速に増加するのに対し、高齢者が元々多い地方では、緩やかに増加する傾向があります。人手不足は一元的に考えるのではなく、地域特性に応じた対策が不可欠とされています。
※ 介護人材確保の現状について/都道府県別有効求人倍率(令和7年3月)と地域別の高齢化の状況|厚生労働省
高齢化の進展に伴う人材需要の増加
都市部では急速に、もともと高齢者が多い地方でも緩やかに高齢化は進展しており、それに伴い介護職の需要も増加しています。
厚生労働省の調査では、2022年度には約215万人とされていた介護職の必要数が、2026年度には約240万人(+25万人)に、2040年度には約272万人(+57万人)に増加すると推計されています(※)。つまり、今後15年で約1.3倍の人材が必要になると見通されているのです。
介護人材の人手不足は業界だけでなく、国全体の問題。こうした需要の増大に対応するため、処遇改善、多様な人材の確保・育成、離職防止と定着促進、介護職の魅力向上、外国人材の受け入れ強化など、国をあげて環境改善や総合的な人材確保に取り組んでいます。
※ 介護人材確保の現状について/9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省
介護・福祉業界が人手不足になる原因と課題

介護・福祉業界の人手不足は、「人気が少ない職種」だからではなく、構造的な要因が絡み合って起こっています。少子高齢化による労働人口の減少、給与・待遇の格差、そして現場の負担の大きさなどが組み合わさることで、人材の確保と定着を難しくしているのです。
ここでは、介護・福祉業界が抱える主な3つの課題を整理します。
人材確保の競争激化と流動性の高さ
まず大前提として、日本社会全体で労働人口が減少傾向にあります。少子高齢化の影響によりどの業界も人材確保が難しく、採用コストが年々上昇しています。
その中でも介護・福祉業界は有効求人倍率が高く、常に多数の求人が出ているため、人材の流動性が非常に高いのが現状です。
せっかく採用しても、より条件の良い施設へ転職してしまうケースも多く、人材がなかなか定着しないという課題を抱える施設も少なくありません。
人手不足がさらなる流動化を招く“負のスパイラル”が生じており、採用だけでなく「定着」に向けた採用活動・仕組みづくりが重要となっています。
給与や待遇面の課題
介護・福祉職は社会的に必要不可欠な仕事でありながら、依然として給与水準が他業界に比べて低いという現実があります。
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、常勤介護・福祉職員の所定内給与額は25万5,400円(※1)。一方、全産業平均の所定内給与額は33万400円と、約7万円の差があります(※2)。
職務内容は身体介助や生活支援など責任が重く、サービス提供のために自分の感情を抑制する「感情労働」的な側面も強いため、「労働の重さ」と「給与の釣り合い」にギャップを感じる人も少なくありません。
処遇改善加算など、業界全体で給与や待遇面の改善は進んでいますが、依然として「安月給」のイメージが拭えず、未経験者が介護・福祉業界を避けたり、経験者が別業界へと移ってしまったりする一因となっています。
※1 賃金構造基本統計調査 / 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種|政府統計の総合窓口
※2 「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果を公表します|厚生労働省
現場の労働環境・長時間勤務・負担の大きさ
介護・福祉現場ではシフト勤務や夜勤、利用者の状況に合わせた急な対応など、柔軟性が求められる働き方が多くなっています。改善は進んでいるものの、現場の人手不足が続く限り、どうしても一人ひとりの業務負担は重くなりがちです。
結果として、残業代はきちんと支払われたとしても、そもそもの長時間勤務や心身の疲弊が蓄積し、離職につながるケースも見られます。
ただし、ライフスタイルに合わせた勤務形態が取れる職場もあり、近年は労働環境の整備も確実に進んでいます。「介護=ブラック」というイメージは必ずしも当てはまりません。
一方で、業界全体のイメージはまだ改善されておらず、業界全体の改善スピードと現場の実感、求職者に対するイメージ改善などのギャップをどう埋めていくかも、人手不足を解消する上で重要になります。
実は、介護・福祉業界は“ホワイト化”が進んでいるんです。他業界と比べても、サービス提供の質や運営体制に問題があれば改善指導が入り、重大な事案は公表されることもあります。
ただし、人手不足によって1人あたりの業務量が多いことは確か。給与など金銭面では改善されても、「人が足りないから休めない」「時間外が増える」という実態もあり、ここをどう解決するかが今後のカギになると思います。
人手不足を解消するための3つの解決策

介護・福祉業界の人手不足は構造的な問題であり、短期間での解決は難しいのが現実。それでも、各施設が「人が定着し、働きがいのある職場」をつくるためにできることがあります。
ここでは、採用と定着の両面から効果的な3つのアプローチを紹介します。
(1)理念中心型の組織運営
介護・福祉業界が抱える課題は一朝一夕に解消されるものではありません。どの事業所にも多かれ少なかれ課題がある中で、採用・定着につなげるカギとなるのが「理念への共感」です。
仕事内容や待遇だけでは他施設との差別化が難しい今、「どんな想いで介護・福祉をしているのか」「利用者や職員に対してどんな姿勢を大切にしているのか」といった運営理念や価値観が、働く人の心を動かします。
理念が明確な組織は、職員が「自分の仕事の意味」を見出しやすく、チームの一体感も生まれます。結果として、採用力と定着率の両方を高めることにつながるのです。
(2)ICT化の推進
介護・福祉の現場では、記録作成やシフト管理、報告業務など、直接ケアに関わらない事務作業が多くを占めています。実際のケアではなく、事務作業が長時間労働を招いている原因となっていることも珍しくありません。
そこで注目されているのが、事務作業のICT化。こうした間接業務をICTで効率化することは、労働生産性向上の重要なカギと考えられており、国・自治体からの補助金も用意されているなど、国の施策としても推進されています。
記録のデジタル化や音声入力、シフト自動作成システムの導入によって、職員が本来の業務に集中できる環境を整えることで、「業務効率」と「働きやすさ」の両立につながります。
事務作業だけでなく、事例の共有や一部の研修などをICT化することで、スキマ時間を使って効率的にスキルアップできる仕組みをつくることもできます。
(3)外国人採用を含む多様な人材の採用
人材不足を補うには、これまで対象としていなかった層にも目を向ける必要があります。
たとえば、アクティブシニアの再雇用、外国人材の活用、介護助手(サポーター)制度、ワークシェアリングの導入など。例えフルタイムでの就業ができなくても、「一部作業を任せられる人材」を採用するのもひとつの手です。
先述した通り、介護・福祉職は事務作業にも多くの時間を要します。ICT化で業務効率化を図ろうと思っても、ICTを導入したり職員がツールを使えるようになるための研修をしたり、実用化するハードルの高さを感じる事業所も少なくないでしょう。
そこで、事務作業を担うスタッフを配置すれば、介護・福祉職員がケア業務に専念できるようにする体制をつくることができます。分業することで一人ひとりの業務負担が減り、長時間残業を防ぐこともできるでしょう。
外国人採用にはさまざまな意見がありますが、実際に現場で働く外国人の方々はとても元気でやる気がある人が多いと感じます。特に若い世代が多く、仕事に前向きな姿勢を持っているのが印象的です。
また、ICT化だけでなく、介護助手などサポート人材をうまく組み合わせることで、介護・福祉職員一人ひとりの負担を減らし、「残業削減」「定着率向上」にもつながります。
介護・福祉現場の人手不足を解消した事例
介護・福祉業界が抱える人手不足の原因と、その解決に向けた具体策を見てきました。では、実際に現場ではどのような工夫や取り組みによって、人材の採用・定着を実現しているのでしょうか。
ここでは、Blanketが介護・福祉事業所と取り組んだ2つの事例を紹介します。
有限会社ダイケイ【人材紹介・派遣利用ゼロ!】

一つ目が、有限会社ダイケイのケースです。ダイケイではもともと専任の採用担当がおらず、代表が一人で採用活動をしていました。
体制が十分とはいえない中、採用率を上げるにはどうしたらよいのか。そこでBlanketでは、まず採用チームの新設と採用活動に関するレクチャーを実施し、ダイケイの採用体制の再構築に取り組みました。
また、既存の採用サイトのデザインは生かしつつ、導線設計や求人情報を充実させることで、会社の魅力をアピール。加えてSNSの運用体制も整えることで、求職者への企業理解を促す取り組みを行いました。
その結果、人材紹介や派遣などを利用せずに応募数を増やすことに成功。さらに、新たな人事制度の構築もサポートすることで、わずか2年間で38%あった離職率を10%に下げることにも成功しました。
詳細は以下の記事で詳しく紹介しています。
社会福祉法人ケアネット【採用コンセプトに即した活動】

二つ目は、社会福祉法人ケアネットが運営する特別養護老人ホーム「さくらほうむ」のケースです。
「さくらほうむ」がある東京都世田谷区は介護人材の有効求人倍率が8倍を超えるほどの激戦区で、人材採用のためには他社との差別化が必要不可欠でした。
そんな激戦区に新規参入するために、Blanketでは事業所の魅力が伝わる採用専用の特設サイトを制作。
事業所の理念や目指すサービスを整理し、「わたしたちがつくるのは、日本一居心地のよい住まいです」というコンセプトメッセージも作成。利用者と職員の笑顔が伝わる写真とともに採用活動に取り組みました。
採用活動全体を通して理念を伝える活動を展開し、徐々に認知度が拡大。その結果、採用激戦区にもかかわらず多くの応募があり、オープニングスタッフも確保することができました。
詳細は導入事例をご覧ください。

まとめ
介護・福祉業界の人手不足は、給与や労働環境の課題、労働人口の減少など複合的な要因によって生じています。しかし、少しの工夫で現場の魅力を伝えたり、職員が働きやすい環境を整えたり、採用率や定着率を高めたりすることもできます。
たとえば、理念中心の組織運営やICT化、多様な人材の活用など。職場の体制や採用体制が十分に整っていない場合でも、専門家に相談することで、事業所に合った具体的な改善策を見つけることができます。
Blanketは、介護・福祉事業所の採用戦略から組織づくりまで、課題に応じたサポートを行っています。人材確保や定着で悩んでいる方は、現状に合わせた最適なプランを詳しくチェックしてみませんか?