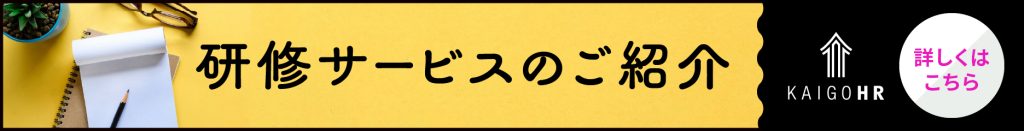職員の介護と仕事の両立を支える。厚労省の新ツールに学ぶ実践のヒント
公開日:2025/11/10 更新日:2025/11/10

介護・福祉の人事・組織づくりを支援するコンサルタント・太田が、話題のニュースやトレンドから、現場で役立つヒントを読み解く連載コラム。今回の“ひとさじ”は、「仕事と介護の両立支援の義務化」がテーマ。職員が安心して働き続けられる職場づくりのために、現場でできる支援のかたちを探ります。
介護と仕事の両立支援を義務化する法改正
家族の介護を理由に職場を離れる「介護離職」は、今やどの業界でも避けて通れない課題です。
厚生労働省の統計によると、毎年およそ10万人が家族の介護や看護を理由に離職しています。特に40〜50代の働き盛り世代に多く、長年培ってきた経験やスキルを持つ人材が離職してしまうことは、組織にとって大きな損失となります。
介護と仕事の両立が難しいまま、疲労や不安を抱え、最終的に退職を選ばざるを得ないという現実が今も続いています。
こうした状況を受けて、改正育児・介護休業法が2025年4月に施行されました。今回の改正では、介護と仕事を両立できる職場づくりを進めるために、事業主に次の取り組みが義務として課されています。
・介護に関する相談窓口の設置
・家族の介護に直面した職員への制度周知と意向確認
・両立支援を進めるための雇用環境整備
これまでは望ましい取り組みとされてきた内容が、今回からは明確に“必ず行うべきもの”に位置づけられました。すべての事業所が介護に関する相談体制を整え、個々の状況に合わせて支援できるようにする必要があります。
こうした流れを踏まえ、厚生労働省は「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を公開しています。このツールは、介護離職を防ぐために企業がどのようなステップで環境整備を進めればよいのかを実務的かつ分かりやすく示したものです。
ツールで示された3つの柱
厚労省の支援ツールでは、両立支援を効果的に進めるための基本的な考え方として、次の3つの柱が示されています。
【1】介護が始まる前から備える「早めの支援」
介護は突然始まることが多く、事前準備ができないまま職員が困難に直面するケースが多く見られます。
そのため、介護が始まる前の段階から情報提供や社内啓発を行うことが重要です。社内報やミーティング、個別面談などを活用して、介護制度や支援策を早めに周知し、職員が安心して相談できる雰囲気をつくります。
【2】安心して相談できる窓口を整える
介護の悩みは、家庭の事情に関わるデリケートな内容を含むため、職場で話しにくいと感じる人が少なくありません。
「迷惑をかけるのでは」「周囲に知られたくない」といった不安から、誰にも相談できずに抱え込むことが離職のきっかけになることもあります。そのため、形式的な設置にとどまらず、安心して相談できる体制づくりが求められます。
小規模な事業所では、管理者や人事担当者が窓口を兼ねる形でも対応できます。
【3】個別対応の仕組みを整える
介護の状況は千差万別です。
介護が必要な家族の状態や支援にかけられる時間、周囲の協力体制によって、必要な配慮も変わってきます。従業員一人ひとりの状況を丁寧に聞き取り、制度周知や意向確認を行ったうえで、記録・共有する仕組みを整えることが推奨されています。
一度きりの対応で終わらせず、定期的な面談やフォローを行うことで、継続的な支援が可能になります。
介護・福祉の現場で考える「両立支援」
介護・福祉の職場は、利用者を支援する立場でありながら、職員自身が家庭で介護に関わるケースも見られます。
「家族の介護が始まったから、夜勤を続けるのが難しい」「親の通院付き添いで勤務調整が必要」といった声は決して珍しくありません。人手不足の現場では、誰かが抜けると業務全体に影響が出やすく、職員本人が「迷惑をかけたくない」と我慢してしまうケースもあります。
こうした事態を防ぐには、「困ったときに話せる場所がある」「理解してくれる人がいる」と感じられる職場づくりが大切です。自社の規模や体制に合った形で、無理のない支援を設計していくことが求められます。
その際、現場に蓄積された知識や経験をどう生かすかが、介護・福祉事業者ならではの強みになります。
現場でできる取り組みのヒント
介護・福祉の事業所では、介護や支援に関する知識や経験を持つ職員がいる場合は、その強みを活かして職員支援の仕組みを考えることもできます。
こうした視点を踏まえ、次のような工夫を取り入れることで、限られた体制でも実効性のある支援を進めることが可能です。
介護をテーマにした社内ミニ研修を行う
地域包括支援センターや社会保険労務士などの外部講師に加え、社内のケアマネジャーや相談員が講師を務めるのも効果的です。
制度の話だけでなく、実際に介護と仕事を両立している職員の体験を共有することで、理解が深まり、安心感が生まれます。
柔軟な勤務調整を可能にする
家族の通院やデイサービス送迎のために、時間単位の休暇や短時間勤務を選べるようにします。
「この曜日だけ早く帰れる」「一定期間だけ日勤にする」といった調整を柔軟に行うことで、職員が働き続けやすくなります。
チームで支え合う文化を育てる
制度やルールだけでなく、日常の中で「お互いさま」と言い合える関係性が大切です。同僚が自然にフォローし合える環境は、安心感とチームの一体感を育てます。
介護に直面した職員を特別扱いするのではなく、誰もが支え合える風土づくりが、長期的な定着にもつながります。
人を支える職場が、信頼を育てる
介護と仕事の両立支援は、特別な制度を導入することよりも、「誰もが安心して働き続けられる環境を整えること」です。
職員が安心して働けることは、そのままサービスの安定と利用者の満足につながります。一人ひとりの事情に耳を傾け、柔軟に対応できる組織こそが、人を大切にできる組織だと思います。
厚労省の支援ツールを活用しながら、社内にある知識や経験を活かして支援の仕組みを整えていく──。
その積み重ねが、安心して働ける職場をつくり、結果として現場の信頼と力を高めることにつながるのではないでしょうか。