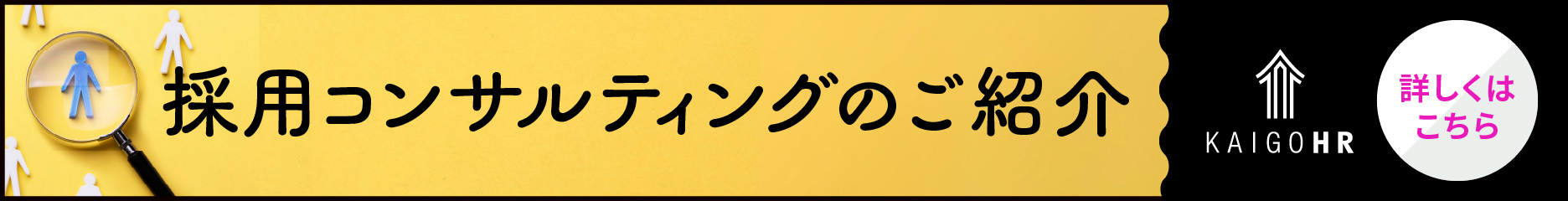若手の「3年離職」を防ぐには。理念と支援でつなぐ定着の仕組み
公開日:2025/11/17 更新日:2025/11/17

介護・福祉の人事・組織づくりを支援するコンサルタント・太田が、話題のニュースやトレンドから、現場で役立つヒントを読み解く連載コラム。今回の“ひとさじ”では、若手の「3年離職」をテーマに、定着に欠かせない視点や具体的な取り組みを紹介します。
若手離職、依然として3人に1人
厚生労働省が2025年10月に公表した令和4年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況によると、就職後3年以内に離職した人の割合は、大卒で33.8%、高卒で37.9%でした。
前年よりわずかに低下したものの、依然として3人に1人以上が就職後3年以内に職場を離れている状況に変わりはありません。産業別では、「宿泊業・飲食サービス業」や「生活関連サービス業・娯楽業」で特に高く、いずれも大卒で5割を超えています。
一方、医療・福祉分野でも、大卒40.8%、高卒49.2%と高い水準で推移しており、若手職員の定着に引き続き課題が見られます。
介護・福祉の仕事は、利用者や家族と信頼関係を築きながら支援を行う専門職です。人材の定着が難しい状況が続けば、チームの安定性やケアの継続性に影響が出やすく、人が育つ前に辞めてしまう悪循環が生まれかねません。
現場の状況に合った育成やサポートの仕組みをどう整えていくかが、今後ますます重要になってきます。
「3年の壁」が生まれる背景
就職から3年の間は、職員が理想と現実のギャップに直面しやすい時期です。現場では、身体的な負担に加え、利用者や家族との関わり方、チーム内での調整など、想像以上のエネルギーを求められる場面が多くあります。
「自分には向いていないのでは」と感じても、忙しさの中で相談できず、孤立してしまうケースも少なくありません。
一方で、組織側にも課題があります。「新人教育をOJTに任せきりにしている」「忙しくて面談の時間が取れない」など、フォローが後回しになりやすい体制では、支援が十分に行き届きません。
また、目標や評価の基準が共有されないまま日々の業務をこなしていると、本人が自分の成長を実感しづらくなり、モチベーションを失うことにもつながります。
こうしたリアリティ・ショック(理想と現実のギャップ)や支援不足を防ぐには、入職前から入職後まで一貫したサポート体制を意識的に整えることが重要です。
現場でできる“3年離職防止”のアプローチ
離職防止の鍵は、制度やルール以上に「関係性」と「仕組みのつながり」にあります。組織の理念や目的を基盤に据え、採用・育成・定着の一連の流れをつなげていくことが大切です。
【1】入職前から「現実と期待の差」を埋める。
採用段階で仕事内容や職場のリアルを正直に伝えることが第一歩です。
たとえば、利用者対応で判断を求められる場面があることや、夜勤明けの体調管理が大切な仕事であることなど、実際の働き方に関わる情報を具体的に共有します。
そのうえで、組織の理念や大切にしている価値観を伝え、「なぜこの仕事をするのか」を一緒に考える時間を持つことが大切です。
理念への共感を採用段階から育てることで、ミスマッチを防ぎ、長期的な定着の土台をつくることができます。
【2】最初の3カ月を“オンボーディング期間”として設計する。
新人が職場に慣れるまでの過程を偶然に任せず、計画的に支援する仕組みをつくります。
オンボーディングとは、入職者が早期に職場に馴染み、力を発揮できるよう支援する取り組みのことです。
【実践の具体例】
・先輩職員によるメンター制度の導入
・「週1回の振り返りミーティング」や「1カ月・3カ月面談」の設定
・小さな成長や努力を認め合う文化づくり
こうした仕組みを組み合わせることで、心理的安全性を高めながら離職の兆しを早くキャッチできます。
【3】理念を起点にチームで育てる。
現場リーダーや先輩職員が、日常のケアや会話の中で「私たちはこういう支援を目指している」と自然に語り合える職場をつくることも大切です。
理念を軸にした対話は、単なる指導ではなく、共に学び合う関係性を生み出します。こうした風土が根づくことで、新人が「自分もこのチームの一員だ」と感じられるようになります。
若手が「ここで働き続けたい」と思う職場とは
「働き続けたい」と思える職場づくりには、離職の要因を正確に把握することが出発点になります。
人間関係、業務負担、評価への不満など、背景を一つずつ丁寧に見直し、スモールスタートでも改善を進める姿勢が大切です。
【実践の具体例】
・人間関係の改善には、対話や関係づくりの機会を増やす。
・業務負担には、ICT活用や業務フローの見直し
・評価には、理念や行動指針に基づくフィードバックを導入する。
また、リーダー層の関わり方も離職防止の大きな鍵です。リーダーが心理的安全性を高め、「失敗しても大丈夫」「一緒に考えよう」と声をかけられる職場では、若手が挑戦を恐れずに成長できます。
「見てくれている」「支えてくれる」と感じられる経験の積み重ねが、長く働きたいという気持ちを育てていきます。
定着は“育成の延長線上”にある
採用して終わりではなく、入職後の数年間を、まずは育成のプロセスとしてどう支えていくか。それが、介護・福祉の現場で人材を定着させるための大切な視点です。
理念を軸に、現場での学びや関係づくり、成長をつなげていくことで、「働きたい」から「働き続けたい」へと意識が変わっていきます。
人材の定着は、仕組みだけでなく日々の関わりの積み重ねによって生まれます。
一人ひとりの声に耳を傾け、誰もが安心して成長できる環境を整えていくことが、結果として現場の力を強くしていくことにつながっていきます。