介護職の効果的な離職対策とは?離職原因からよい職場づくりまでわかりやすく解説
公開日:2025/09/12 更新日:2025/11/17
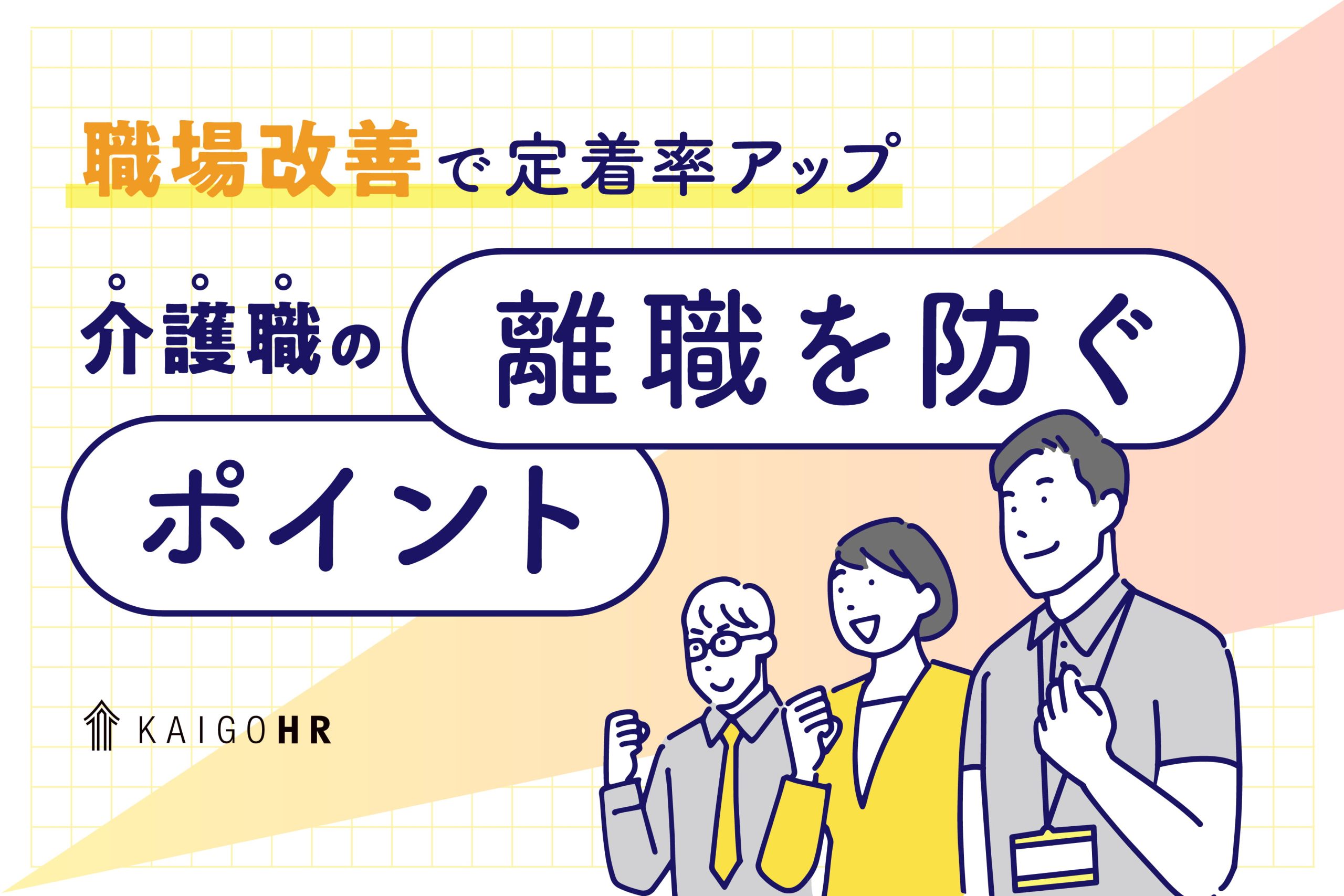
介護業界の人材不足の根本的な原因である「離職」。職員の定着率の低さに、頭を抱える介護施設は少なくありません。
離職は現場の負担増やサービス品質の低下を招き、施設運営にも直結する問題です。離職予防には、離職の原因を正しく把握し、自事業所の実情に合った対策を講じることが鍵となります。
そこで今回は、介護職の離職状況や背景、離職を防ぐための具体的なポイントを、介護・福祉業界に特化した採用・人事コンサルタント監修のもと紹介します。施策を取り入れて定着率向上を実現した事例も解説するので、介護施設の運営者・人事担当者はぜひ参考にしてください。

【監修者】
野沢 悠介
株式会社Blanket取締役 / 人事コンサルタント / ワークショップデザイナー / 国家資格キャリアコンサルタント / Career Development Adviser
介護職の離職状況と離職対策が必要な背景

介護業界では採用活動の難しさだけでなく、慢性的な離職率の高さも課題の一つです。一度採用した職員が長期的に働くためには、離職のきっかけ・現状・背景を理解する必要があります。
ここでは介護職の離職率や主な理由と対策が急務とされる背景について見ていきましょう。
介護職の離職率の現状
厚生労働省の推計によると、2040年には約280万人の介護人材が必要になるとされています(※1)。しかし、令和5(2023)年10月1日時点での介護職員数は約212.6万人にとどまり、前年(令和4年)からは約3万人減少しました(※2)。
この背景には離職の多さがあります。介護職の離職率は近年は低下傾向にあるものの、全産業平均と比べるとやや高い水準です。
介護現場の離職理由として多いのは、人間関係による心理的負担や施設方針との価値観のずれ、労働条件のより良い業種や別の施設への転職などが挙げられます。
※1 介護人材確保に向けた取組について | 厚生労働省
※2 介護職員数の推移の更新(令和5年分)について| 厚生労働省
なぜ介護職の離職対策が今求められているのか
離職は、職員のモチベーション低下を招き、人材不足の現場では一人抜けるだけで他の職員に大きな負担がかかります。「いつまでこの状況が続くのか」「あの人が辞めたなら自分も…」と連鎖的に離職が起こることも少なくありません。
さらに人員不足はサービス品質の低下につながり、施設運営にも直接影響します。子育てや家族介護との両立が必要な人にとっては、過酷な勤務条件が離職の決定打となるケースもあります。
こうした介護現場の人手不足を受け、国も離職防止策を進めていますが、現場で十分な成果はまだ出ていません。だからこそ施設側が国の施策と連携し、自社の状況に合った離職対策を講じることが、今まさに求められているのです。
全産業で人手不足が深刻化する現在は、「採用できるか」だけではなく、「採用した人がどれだけ長く働けるか」も問われる時代です。
介護職が離職しやすい理由と対策のポイント
自社の介護職員の離職を防ぐためには、まず原因をしっかりと把握し、その要因に沿った対策が必要です。ここでは介護現場でよく見られる3つの主な離職理由と、それぞれに有効な改善策を見ていきます。
業務の負担感と低賃金のギャップ
介護職は、利用者の生活を支える介助に加えて、その家族との関わりも生じる仕事です。肉体面だけでなく精神的な負担も大きい仕事であることから、従業員が心身ともに疲弊してしまうケースもあります。
ところが、そうした過酷な業務内容であるにも関わらず「見合う報酬が得られていない」と感じる現職員は少なくありません。正当な対価を得られないことから仕事へのモチベーションが低下し、それが離職につながることもあります。
対策例としては、勤務時間の調整や休憩時間の確保、賃金水準の見直しや手当の充実など、労働環境そのものを改善する取り組みが有効です。
介護業界の給与は、ここ20年で上がってはいます。しかし、報酬の上限が公定価格で決まるという構造上、自助努力での大幅な賃上げは難しく、他業界と比較すると上昇幅はそれほど大きくありません。施設側の採用単価の高騰も、人手不足の悪循環を招く原因となっています。
働きづらさ(人間関係・シフト・ライフイベント)
介護職の離職理由として特に多いのが、人間関係によるストレスです。チームワークが欠かせない現場ですが、世代や経歴、職種が異なる人が集まることが多いため、摩擦が生じやすい傾向にあります。
こうした人間関係による「働きづらさ」を改善するためには、職場内のコミュニケーション促進が欠かせません。人事・運営側は従業員と定期的な面談を行い、現職員の状況を理解することで改善策が見えてきます。
また、夜勤や休日出勤などシフト制での勤務のため、家庭との両立の難しさを感じる職員も少なくありません。そのため結婚や出産、親の介護といったライフイベントで離職に至るケースもあります。
こうしたシフトの課題を解決するには、複数名での夜勤体制や短時間勤務枠の導入など、柔軟に働けるスケジュール管理や育児・介護休暇制度の活用を推進することが有効です。
キャリアパスや成長機会の不透明さ
将来の働き方や成長の道筋が見えないことも、介護職員の離職の大きな要因です。スキルアップや昇進のルートが明確でないと、先行きに不安を感じやすくなります。
加えて教育や研修体制が十分でない職場では成長の機会が限られ、やりがいを失ってしまうこともあります。
対策例としては、キャリアパスの整備や定期的な研修の実施、資格取得の支援など、長期的に働ける環境づくりが求められます。
上記のような施策を展開するためには、安定的な人材の確保が必要となり、新規採用が行う仕組みも重要となります。採用力の強化とよい組織づくりは、どちらか片方では難しく、少しずつでも両輪で進めていくことが重要です。
効果のある介護職の離職対策とは?

離職対策は制度や施策を並べるだけでは成果は出にくく、自社に合った方向性を見極める必要があります。ここでは、採用・定着支援の現場を多く見てきたBlanketならではの視点も踏まえ、効果的な離職対策のポイントを紹介します。
理念を明確にする
介護施設ごとに「求める人物像」は異なります。自社が求める人材と雇用した人材にズレがあると、現場職員との摩擦が生じやすくなり、離職率の後押しをする原因になります。
こうしたミスマッチを避けるためには、理念を明確にすることが重要です。
採用段階から理念を基にした働き方の方針を伝えることで、ミスマッチを減らし長く働きたいと思える人材を集めやすくなります。
理念が浸透すると、「何のために働くのか」が全員で共有でき、離職防止の土台になります。
教育制度の充実でスキルアップと定着を促進
未経験者や経験の浅い職員にとって、入職後の教育体制は安心感につながります。
オンボーディングの流れや役割の説明、業務の進め方などを整備し、新職員が現場に早く馴染める環境をつくりましょう。定期的な研修や資格取得の支援を行うことも有効です。
こうした対策は、成長意欲の高い職員のモチベーション維持にもつながります。
労働環境の改善で負担軽減を実現
「休みを取りにくい」「労働時間が長く休憩時間が短い」といった労働環境の悪さも、離職の大きな原因となります。
勤務時間の調整や休憩時間の確保、夜勤や休日出勤の負担軽減など、シフトを調整しやすい環境を整えることが介護職の離職対策には重要です。
人員の少ない介護現場でシフト環境の調整が難しい場合は、手当の充実化に注力するのも良い方法です。労働に対して正当な対価を得られている、と感じることができればモチベーションの維持につながります。
フォローアップ体制の強化で安心感を提供
多くの職員は、ある日突然離職を決意するのではなく、小さな違和感の積み重ねで離職を意識していきます。
そうしたタイミングを見極め、不満をすべて防ぐことは難しいですが、気軽に悩みを共有できる場を設けることで、小さな不安が離職に発展することを防げます。
定期面談や相談窓口の設置、メンター制度など、職員が不安や不満を抱いた際に吐き出せるフォローアップ体制を整備しましょう。
外部サービスの利用
介護業界にも人事・組織課題解決コンサルティングといった外部サービスが存在します。こうした外部の専門サービスを活用することで、課題がより明確に見えてくることがあります。
また、第三者の客観的な視点が加わることで、これまで気づいていなかった自社の魅力を発見できることも少なくありません。
コスト面の懸念から外部サービス導入をためらうケースもありますが、離職による採用コストや人員不足の影響を考えれば、投資する価値のある取り組みです。
採用から定着までを包括的にサポートできる外部機関を上手に活用することで、社内だけでは実現しにくい効果を得られるでしょう。
外部の力を借りることで、変化を加速させる近道になります。
介護現場で取り組みたい離職対策の具体例
離職対策は、各事業所の課題や特色に合わせた取り組みが必要です。しかし限られた人員の中で有効な方法を探り、実践するのは簡単ではありません。本格的な離職対策を実現するのであれば、外部サポートの力を活用することも検討してみましょう。
ここでは、介護・福祉業界に特化した採用・定着支援を行うBlanketが実際にサポートし、離職率が低減した好事例を2つご紹介します。
(1)有限会社ダイケイ(介護事業所「笑楽日」)

有限会社ダイケイは、福井県で有料老人ホームやデイサービスを運営する企業です。かつては離職率38%に達していた同社は、定着率の安定を実現するために、Blanketによるサポートを受けながら人事制度を全面的に見直しました。
その結果、汎用的で評価方法が不明確だった人事制度に大きな変化が生まれました。
まず、Blanketの提案のもと、スタッフを巻き込んだワークショップを行い、理念や課題を整理し5つの評価軸と等級制度を策定。さらに給与と連動する評価シートを導入し、リーダー層による面談で目標設定や評価基準を共有しました。
施策の導入によって、評価基準が明確になり、昇給や賞与決定の納得感が向上。それだけでなく制度づくりの過程も職員の意欲向上と組織の一体感を生む結果につながり、定着率が安定するようになりました。
(2)社会福祉法人大和会

奈良県で高齢介護支援事業を展開する社会福祉法人大和会は、地域の労働人口減少や通勤困難な立地により、採用と定着の両面で課題を抱えていました。
Blanketは、現場職員へのヒアリングで「大和会らしさ」を言語化し、魅力や強みを共有。これにより施設全体の意識改革が進み、定着率向上の土台が整いました。
同時に、その魅力を活かしたスカウトメール配信や採用サイトを改善し、Instagram運用支援などで応募獲得にも成功。2か月で5名の応募があり、その後も継続的な応募が続いています。
組織課題の改善と採用強化を並行して進め、職員が働き続けやすい環境づくりと人材確保の両立を実現した好事例です。
介護職の離職対策に活かせる支援制度と相談窓口・外部サービス
離職対策は、施設や事業所が独自に取り組むだけでは限界があります。国や自治体が提供する制度や相談窓口、さらには外部の専門サービスを活用することで、より持続的な対策が可能になります。
ここでは、自社の取り組みを後押しする代表的な制度やサービスをご紹介します。
制度は「知っている」だけでなく「活かす」ための運用が大切です。
厚生労働省による制度支援の活用
「介護職員処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」などの金銭的支援は、職員の待遇改善に直接つながります。
ほかにも「職場環境改善助成金」や「人材確保支援事業」など、職員の定着に向けた制度も複数あるので、ぜひ活用しましょう。
また制度を活用する際は、加算の条件や申請スケジュールを把握し、計画的に取り組むことが大切です。
参考:
「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内|厚生労働省
「介護人材確保・職場環境改善等事業」のご案内|厚生労働省
自治体・地域包括支援センターなどの相談窓口
自治体による介護人材支援課や福祉人材センターなどは、人材確保や定着支援に関する相談を受け付けています。
また、社会福祉協議会や地域包括支援センターでは、職員やその家族のメンタル面、家庭事情に関する相談にも対応が可能です。
こうした地域の特性に合わせた情報や助成制度も用意されています。内容は自治体ごとに異なり、定期的に条件などが更新されるため、つねに情報収集のアンテナを張っておくと良いでしょう。
介護職採用を支援する外部の支援サービス

介護業界に特化した人材コンサルティングや定着支援会社など、外部の専門機関を活用することで、自社だけでは見つけにくい課題や改善点が明らかになります。
Blanketでは、施設ごとの課題や強みに合わせた具体的な改善施策を提案し、採用から定着まで一貫したサポートを行っています。離職対策を検討している担当者の方や施設は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
離職率を改善することは、現場の負担軽減やサービス品質の向上、採用コストの削減など、多くのメリットにつながります。
そのためには理念の明確化や教育制度の充実、労働環境の改善、フォローアップ体制の強化といった施策を、自社の状況に合わせて実行していくことが大切です。
こうした取り組みは職員が「長く働きたい」と思えるだけでなく、結果として利用者やその家族の安心にもつながります。
ただし、現場の業務と並行して制度設計や環境改善を進めるのは簡単ではありません。課題の洗い出しや具体的な施策の実行に悩む場合は、外部の専門家に相談し、伴走してもらうことも選択肢の一つです。
正解は一つではありません。一緒に考えてくれる人がいれば、きっと道は見つかります。まずは気軽にご相談ください。







