視点の転換で組織が変わる──安斎勇樹氏に学ぶ、介護・福祉業界の“冒険する組織”の5つのレンズ
公開日:2025/07/09 更新日:2025/08/28

「チームに課題があり、なんとかしたい。でも、何をどう変えればいいのか分からない」
介護・福祉の現場づくりを担う経営者や管理者の中には、そんな声なき焦りやモヤモヤを抱えている方も多いのではないでしょうか。
「KAIGO HR FORUM 2024」に登壇した、組織開発やキャリア論の研究・実践の第一人者であり、さまざまな企業や自治体の組織変革を支援してきた安斎勇樹氏。安斎氏が投げかけた問いや示した“冒険的世界観”という視点は、今の介護・福祉現場に新しい風を吹き込み、これからの組織づくりのヒントとなるものでした。
前編では、その全体像とポイントを整理しました。今回はさらに一歩踏み込みます。安斎氏が最新刊『冒険する組織のつくりかた』で提案する「5つのレンズ(目標/チーム/会議/成長/組織)」をヒントに、現場での具体的な実践策を探っていきます。
コラムの前編「働きがいと探究が交差する組織へ──安斎勇樹氏講演をヒントに考える介護・福祉の『冒険的世界観』」もあわせてご覧ください。
“冒険する組織”のコンパスとなる「5つのレンズ」
安斎氏は、“冒険する組織”を実践するヒントとして、「5つのレンズ」という視点を提示しています。組織を「管理するもの」としてではなく、「探究し共創する場」として捉え直すために、組織の捉え方を意識的にアップデートするためのフレームです。
組織とは、何を達成するための仕組みなのか。人はなぜ働くのか──。こうした根本的な問いに対し、これまでの“軍事的世界観”ではなく、共創や探究を軸にした“冒険的世界観”で捉え直すための視座が、この5つのレンズです。
目標のレンズ:みんなの好奇心をかき立てる「問い」であるべきという視点
チームのレンズ:同僚や部下は機能的な「道具」ではなく、個性を活かし合う共同体として捉える視点
会議のレンズ:伝達や意思決定の場ではなく、対話と価値創造の場とする視点
成長のレンズ:スキルや行動変化による“古い学習観”から脱却し、組織の学びそのものを問い直す視点
組織のレンズ:管理や統制ではなく、人と事業の可能性を広げる土壌としての視点
これら5つの視点は、いずれも介護・福祉の現場においても、そのまま活用できる実践的なヒントに満ちています。ここからは、特に介護・福祉業界にとって重要だと思われる「レンズ」にフォーカスし、具体的な実践の可能性を考えていきます。

目標のレンズ:意味をともにつくる“希望の指標”
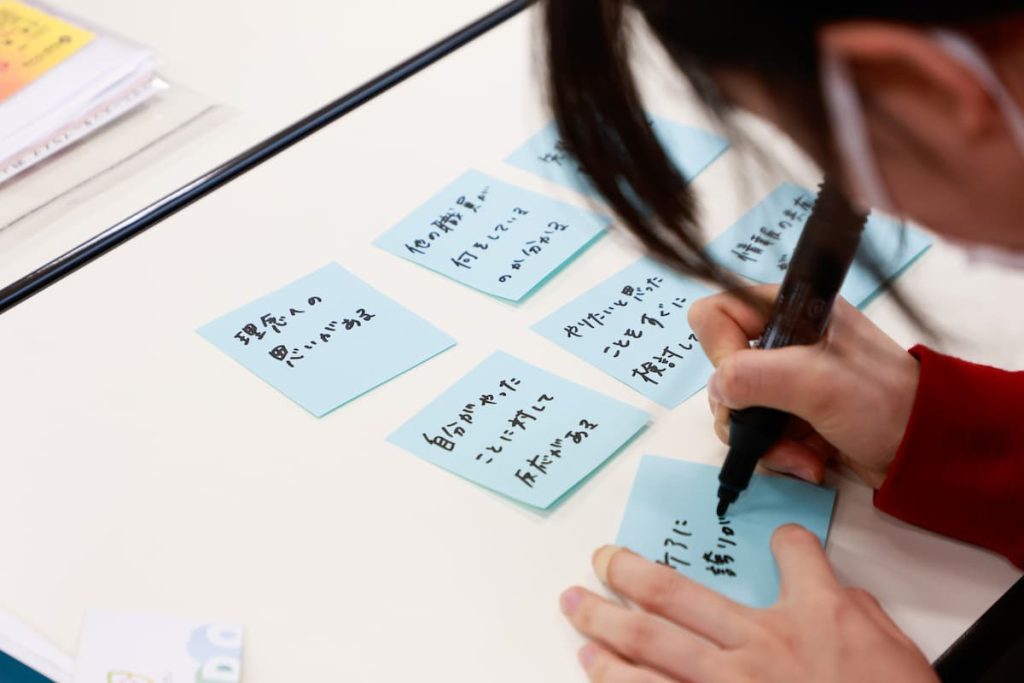
介護・福祉業界では、「キャリアの方向性が見えない」「やりがいを見失った」といった理由で離職していく職員が少なくありません。
一方で、事業所側も「どんな目標を提示すれば、職員の成長を支援できるのか」と頭を悩ませるケースが多くあります。
その背景には、従来の“軍事的世界観”による目標設定──つまり「数値」「期限」「成果達成」といったトップダウン型の管理手法が、介護・福祉という仕事の本質と噛み合っていないという、構造的なズレがあるのではないかと、安斎氏のお話を聞いて改めて感じました。
介護・福祉の仕事は、効率や成果だけでは測れない、「人の幸福」や「日々の暮らしを支える丁寧な関わり」を大切にする営みです。
そして、この仕事を選ぶ人の多くは、「誰かの役に立ちたい」「目の前の人に寄り添いたい」といった、価値志向型のモチベーションを持っているといえるでしょう。
だからこそ、目標もまた、上から与えられるものではなく、
・「この場所で、この組織で、私たちは何を大切にしたいか」
・「どんな価値を、誰に届けていきたいか」
といった問いから出発し、職員と共につくるものである必要があるのではないでしょうか。
介護・福祉の現場がもともと持っている“人と人との関係性”や“他者の幸福を願う営み”といった特性を考えると、このような意味をともにつくる目標のあり方は、介護・福祉業界にこそ自然にフィットするのではないでしょうか。
例えば、こんな小さな取り組みから始めてみるのもよいかもしれません。
・「ケアの中で大切にしたいこと」を共有する対話の場を定期的に設ける
→ 数値目標の共有ではなく、「今の仕事で心を動かされたこと」や「自分たちが大切にしたいケアの姿勢」などを語り合い、目標の土台に“意味”を育てる時間をつくる。
・個人の価値観に根ざした目標シートの作成
→ 法人全体の目標に加え、「自分がこの1年で実現したいこと」「目の前のご利用者にどう向き合いたいか」といった個別の目標設定をサポートし、それをもとに対話することで、自己実現と組織的ミッションの重なりを見つける。
こうした対話的・共創的な目標づくりのプロセスを通し、職員一人ひとりの価値観に光を当て、共に意味を編み直していくことが、結果として離職防止や成長支援につながるのではないでしょうか。
成長のレンズ:プロセスをたたえる“探究のまなざし”
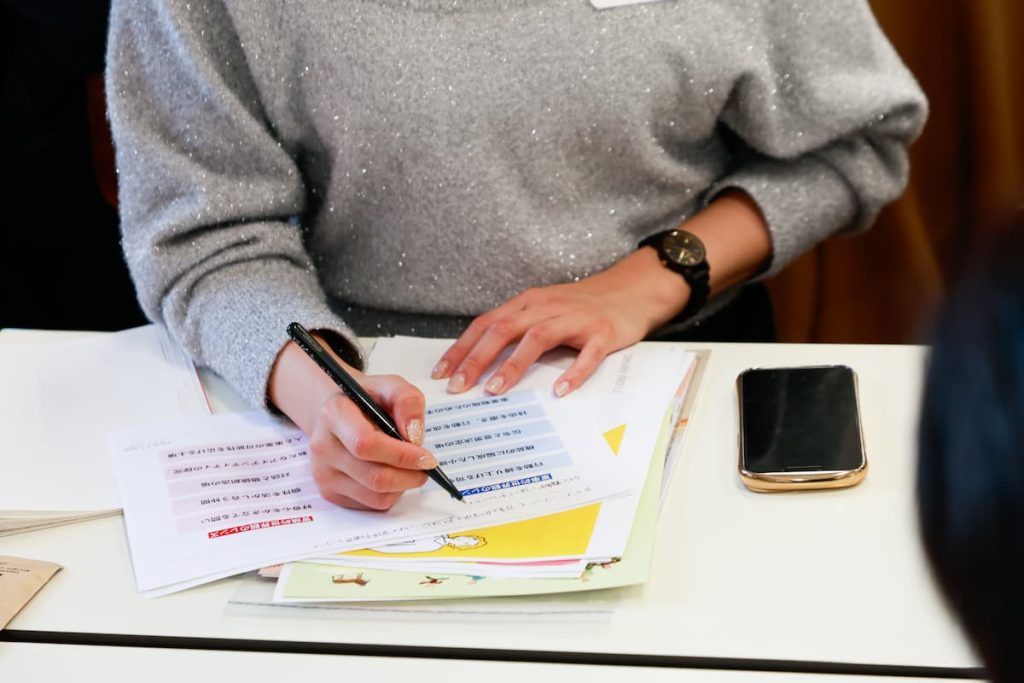
介護・福祉の現場では、「成長=できることが増えること」「評価に反映されるスキルや成果」として捉えられることが少なくありません。たとえば「ミスを減らす」「記録を早く書けるようになる」「リーダー的役割を担う」といった“結果”が成長の証として注目されやすい構造があります。
しかし、安斎氏が提唱する“成長のレンズ”は、そうした成果主義的な見方に一石を投じます。成長とは「評価される結果」ではなく、「問いを持ち、アイデンティティが変化し続けるプロセス」にこそ宿るという視点です。
介護・福祉の仕事は、日々同じようでいて、実は一人ひとり異なるご利用者と向き合う創造的な営みです。「昨日の正解が今日も正解とは限らない」――そんな状況で、職員が“問いながら働く”ことを支える風土こそが、深い意味での成長を育む土壌になるのではないでしょうか。
そのためには、「何ができたか」だけでなく、「何を悩んだか」「どう考えたか」「そこから何を学んだか」に目を向ける文化が必要です。
たとえば、こんな取り組みが考えられます。
・「成長ジャーナル」の導入
→ 日々の仕事で感じた気づき・違和感・問いを短く書き留める習慣を推奨し、業務日誌では見えにくい“内面の成長”に光をあてる。
・定期的な「ふりかえり対話」の仕組み化
→ 上司との面談やチーム内ミーティングの中に、「最近迷ったことは?」「気づきがあった出来事は?」など、プロセスに焦点を当てた質問項目を取り入れる。
こうした“プロセスをたたえる文化”が根づけば、失敗も「試行錯誤の証」として肯定され、職員が萎縮することなくチャレンジし続ける環境が育まれるでしょう。
これは、結果として職員の自律的成長を促し、組織の創造性や柔軟性の向上にもつながるはずです。
チームのレンズ:関係性を耕す“共創の土壌”

介護・福祉の現場では、職種間・シフト間・事業所間など、複数のチームが連携しながらケアを届ける必要があります。しかし現実には、「情報共有が足りない」「連携がうまくいかない」「チームの雰囲気がギスギスしている」といった声も少なくありません。
安斎氏が提唱する“チームのレンズ”は、こうした状況を「役割分担や指示命令の問題」だけでなく、「関係性の質」に着目して見直す視点を与えてくれます。
「冒険的世界観」におけるチームとは、「共に問い、共に意味をつくる関係性の場」としての意味を持ちます。
介護・福祉の現場には、もともと“人と人との関係性”を大切にする文化があります。だからこそ、単なる連携を超えて「関係性そのものを耕す」意識が、チームの土壌を豊かにし、協働の質を高めていく鍵になるのではないでしょうか。
たとえば、以下のような取り組みがその一歩になります。
・「チーム対話の時間」をシフトに組み込む
→ 日々の業務報告とは別に、「最近感じたこと」「うまくいったケア」「迷った場面」などをフラットに共有する雑談的ミーティングを設けることで、互いの価値観や感情に触れる機会を増やす。
・「ありがとうカード」や「エピソード共有ボード」を導入する
→ 日々の中での小さな感謝や気づきを記録・共有するツールを設け、業務を超えた関係性の中に“肯定的なまなざし”が生まれるきっかけをつくる。
こうした“関係性を耕す”小さな仕掛けが、安心して声を出せる風土をつくり、結果としてケアの質や職員の定着率にもつながっていくのではないでしょうか。
小さな視点の転換が、冒険する組織への第一歩に
今回は「目標」「成長」「チーム」という3つのレンズに絞って、介護・福祉業界での実践にどうつなげていけるかを考えてみました。残りの「会議」「組織」のレンズも、きっと現場に新たな視点と可能性をもたらすはずです。
こうして整理してみると、まず大切なのは、上司・リーダー自身が“ものの見方”を問い直し、新しいレンズで組織を眺めてみること。 そのうえで、現場で起きていることや、職員との関わりに、これまでとは違う問いやアプローチを投げかけてみることが、“冒険的組織”への第一歩となるのではないでしょうか。
今、介護・福祉の現場では、制度や人手不足といった構造的な制約のなかでも希望をあきらめずに現場を支え続けている管理者・リーダーの存在が欠かせません。だからこそ、「この職場でなら、働き続けたい」「このチームとなら、また挑戦してみたい」 そう思える“冒険的な現場”を、ぜひあなたの組織からぜひ創り出していきましょう。

【この記事を書いた人】
株式会社Blanket取締役/人事コンサルタント
野沢 悠介
立教大学コミュニティ福祉学部卒。介護事業会社で、採用担当・新卒採用チームリーダー・人財開発部長などを担当後、2017年より現職。介護・福祉領域の人材採用・人材開発を専門とし、介護・福祉事業者の採用・人事支援コンサルティングや、採用力向上のためのプログラム開発、研修講師などを中心に「いきいき働くことができる職場づくり」を進める。







